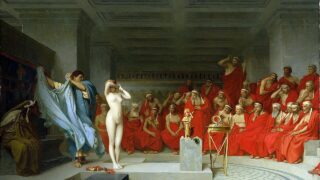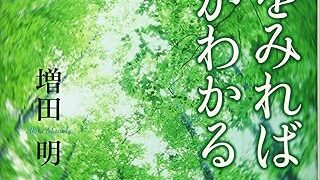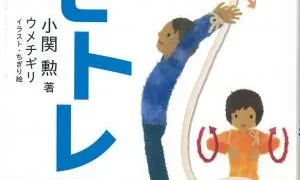エウレーカ

わたしが小学生くらいの頃には、「まんが世界の伝記」というシリーズがありました。今探してみると、複数の出版社が似たようなラインナップで、偉人の伝記を出しておられるようです。そういえば、似たような、でも微妙に違うまんがを見比べたような記憶もあります。
わりとエピソードとして奇天烈なのが、「お風呂から飛び出してそのまま街中を走り抜けた」という「エウレーカ」あるいは「ユリイカ」と称される、アルキメデスの物語です。アルキメデスが浮力の原理をみつけた、というエピソードですが、当時のローマは暖かかったのでしょうか。
他にも野口英世とかナポレオンとか、いろいろなラインナップが並ぶのですが、定番の偉人として「ヘレン・ケラー」というのもありました。「三重苦の…」と前置きがつくのが、これまた定番で、圧巻は、井戸のポンプのところで「ウォーター!」って泣き笑いする、というシーンになっています。
これまたわたしの思い出ですが、小学校だか、中学校の芸術鑑賞で、学校に劇団がやってきて、体育館で観劇した記憶があります。そのうちの一回が、このヘレン・ケラーの物語の再現…「奇跡の人」でした。「あー。ウォーター!ね…」と思いながら見ていたように思います。
舞台の上で実際に水が出てくる手押しポンプの仕掛けが不思議でした。
よくよく考えると、偉人、として挙げられていますが、ヘレン・ケラー女史は、さほど大きな成果をあげておられる方、というわけではありません。いや、視覚障害と聴覚障害を幼少期に抱えつつも、それでたくさんの業績を残しておられるそうですから、十二分に大きい、という言い方もできます。が、いわゆる発明発見のそれとはちょっと違うし、時代を変えた、というわけでもない。それでも、劇の題材になり、小学生が読むまんがになっている、ということについて、ふと考えてみました。
話が急に変わるのですが、数学の研究者の森田真生という方がおられます。大学に所属せず、独立研究者として仕事をされている方ですが、「数学の演奏会」という名前の講演会なさっていたりしたのを、一時期ずいぶんと追いかけて、話を伺っていました。
氏の話は大変にエキサイティングで、話を聞くだけで頭が活性化されるような、そんな心持ちになったので、是非どこかでご紹介したいのですが、いつだったか、氏が「正解を教わってしまったら、その問題は2度と解けなくなってしまう」という発言をされていました。
「問題を解く」という言葉の意味が違うわけです。
普通の勉強では、問題の解き方を習うわけです。で、その方法を応用して問題を解く…と言うわけですが、これは、「回答にたどり着く」ということになります。
ところが、それは、自分の思考で作り出した道筋ではありません。数学者としては、そのような、定型で手を動かしたら得られる回答がたとえ「正解」であっても、その点にはあまり価値がない、ということなのでしょう。
それよりも、自分の手持ちの道具と知性を発揮することで、その問題の回答への道筋を、自分自身で作り上げることこそが、「問題を解く」という言葉にふさわしいのでしょう。
一方で、こういった形で先人の知恵をあまり参照しないまま、我が道を行くと、なかなか残念なことにもなりかねません。数学の研究者は時々、在野の方がおられるそうですが、長年、独自で研究をなさっていた方が、自信満々に連立方程式の解法を発見した、と発表された、という残念な話も聞かせていただきました。まさに「車輪の再発明」です。
学問の蓄積は馬鹿になりません。他者が積み上げてきたものがあるからこそ、わたしたちはその巨人の肩に乗るような視野を得られているわけです。
とはいえ、自分自身で獲得することも、やはり大事なわけです。
自分で意味を獲得した、ということの典型が、ヘレン・ケラー女史の「ウォーター!」にはちりばめられていて、お勉強して、記号をたくさん記憶することと、世界には意味がある、と発見することの違いを、あのシーンは鮮烈に描き出しているのだ、と理解することができるわけです。
と、ここまで書いてきてふと思いました。
ヘレン・ケラー女史の物語も「水」に関わるものでしたが、アルキメデス氏の発見も、水にまつわるものです。水に触れる感覚が、なにかそういう発見を呼び起こす、よい刺激になっているってことがあるのかも知れません。