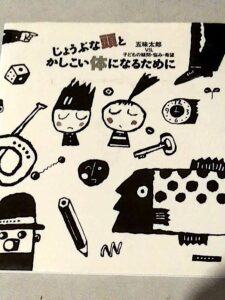タイトルが先か中身が先か
文章を書くときに、記事のタイトルをどうつけるのか、って、真面目に考えはじめると、けっこう難しかったりします。
本の題名などは、中身の要約だけじゃなくて、読者向けのアピールポイントにもなりますので、じっくり考えた方が良いのでしょう。
昔、「本の売れ行きを決める要素のほとんどはタイトルと表紙だ」とおっしゃる先生がいらっしゃいました。
たしかに表紙を変えただけで劇的に売れるようになった本があったりしますので、あながち見当違いとも言えません。
2007年には『人間失格』が表紙を変えたことで劇的な売上増を示しました。
当時ブレイクした漫画家が表紙を描いたことで、漫画読者の層にアピールが突き刺さったようです。こちらはタイトルが変わったわけではありませんが…。
わたしがブログの記事を書くときには、おおよそのテーマを決めて、それに関連したタイトルを持ってきて、仮置きします。
その上で、つらつらと文章を綴ります。
できあがった本文を見て、タイトルとのズレがあまりにも大きい時には、改めてタイトルをつけなおす、ということにしています。
ざっくり言うと、「あまり考えていない」という結論に到達しそうですが…。
本文の長さをどのくらいにするのか、というあたりも、わりといい加減です。本文が長い日と、短い日があります。
無理に字数を稼ごうとも思っていませんが、わたしは油断していると文章が長くなってしまうタイプなので、ついつい長いブログが多くなっています。
文章を書くたびに「もっと簡潔に!」と叱られるようなことがありましたが、そこからあまり成長せずに過ごしてしまいました。
わたしが本を買うときには、中身が重要なのか、それとも見た目やタイトルが重要なのか?と訊かれると、これまた難しいです。
中身ももちろん重要ですが、ジャケット買いをしないのか?というと、まれに、ジャケット買いに近いことをしたりします。
先日は井伏鱒二氏の『厄除け詩集』というのをジャケット買いしました。「厄除け」ってなんだよ?って思ってしまったらダメでしたねえ。
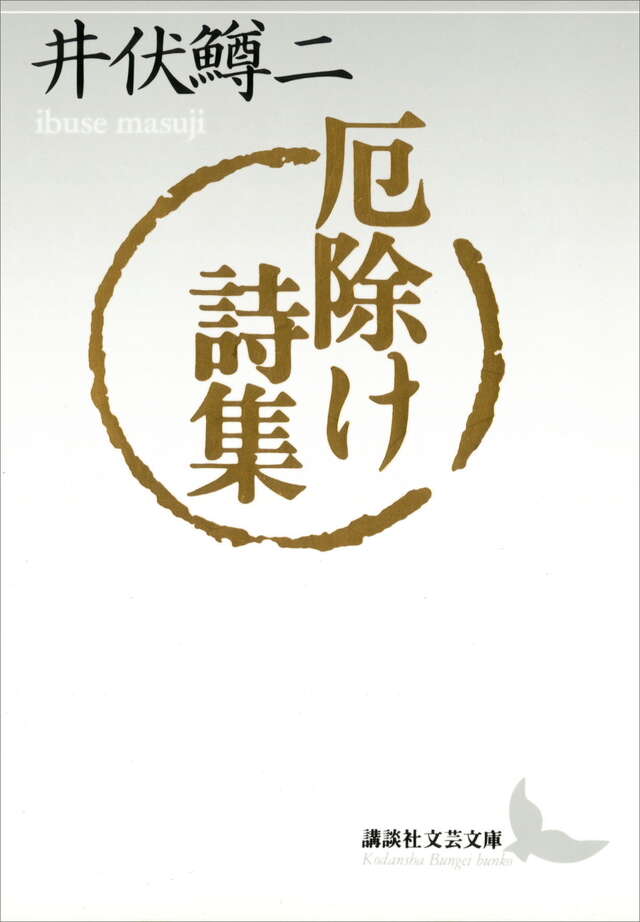
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000167670
井伏鱒二氏は、わたしが若い頃(中学生だったでしょうか…?)に読んだ『ドリトル先生物語』を翻訳された方でもありました。
当時、文中で、「しあわせ」を「仕合わせ」と書いておられたのがすごく印象的でした。こういう書き方があるんだ…と感心したものでした。
うまいこと「仕」が「合」うことを「しあわせ」と呼ぶのだ、というのは、とても文学的な表現だなあ、と思ったのでした。ここは井伏氏のセンスが光っていたのだと思います(当時はそういう書き方が一般的だった…とかいうこともあるのかもしれませんが)。
ボディートークの師匠である、増田明氏に言わせると、「幸」の字は「執」の字の左側で、これは「丸」の部分がヒトで、それを「手枷」にかけているのが「執」であるのだ、と。とらわれているから「執」なわけです。で、その「とらわれているわけじゃなくて、良かったね」というのが「幸」なのだ、と説明していました。なんとも難しい物言いだなあ、とは思ったのですが、「幸」の字があまり素直に「しあわせ」を言い表しているものでもなさそう…ということだけは理解しました。
まあ、「しあわせ」って、抽象的な概念でもありますから、象形文字で書き表すのも難しいですよねえ。
文字にあらわすことも、タイトルにあらわすことも、そのくらい「ズレること」があるのだ、というくらい、ふんわり諦めているのがちょうど良いのかもしれません。