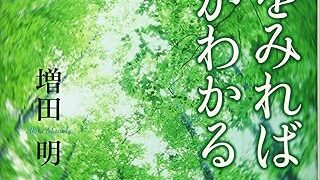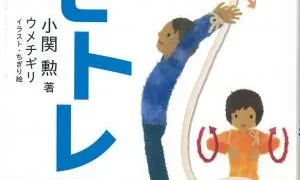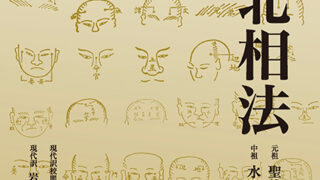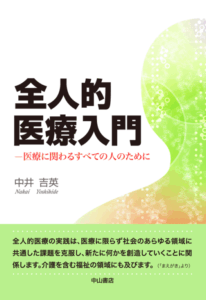ホリスティック医学
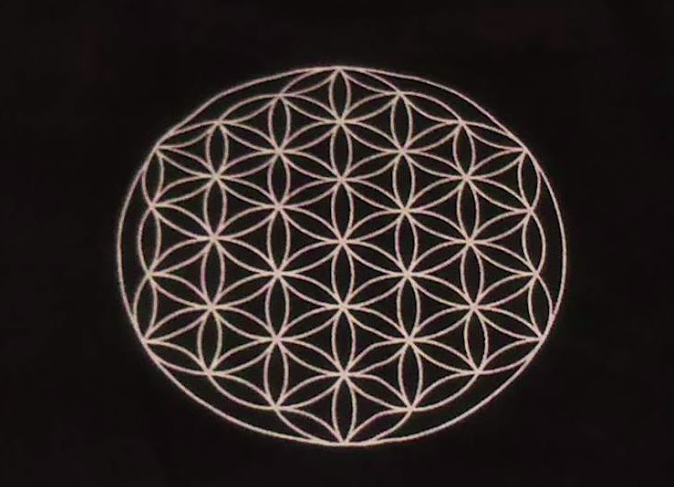
先日、全人的医療という話についてブログを書くために、全人的医療とか全人医療みたいな単語でネット検索を続けていたら、横文字の「ホリスティック医学」というものにも出会いました。
ホリスティック??うん?って思ったら、全体的な、みたいな意味らしいです。それを掲げた団体がありました。
NPO法人 日本ホリスティック医学協会では、「ホリスティック医学」を次のように定めています。
① ホリスティック(全的)な健康観に立脚する
人間を「体・心・気・霊性」等の有機的統合体ととらえ、社会・自然・宇宙との調和にもとづく包括的、全体的な健康観に立脚する。② 自然治癒力を癒しの原点におく
生命が本来、自らのものとしてもっている「自然治癒力」を癒しの原点におき、この自然治癒力を高め、増強することを治療の基本とする。③ 患者が自ら癒し、治療者は援助する
病気を癒す中心は患者であり、治療者はあくまでも援助者である。治療よりも 養生、他者療法よりも自己療法が基本であり、ライフスタイルを改善して患者自身が「自ら癒す」姿勢が治療の基本となる。④ 様々な治療法を選択・統合し、最も適切な治療を行う
西洋医学の利点を生かしながら中国医学やインド医学など各国の伝統医学、心理療法、自然療法、栄養療法、手技療法、運動療法などの各種代替療法を総合的、体系的に選択・統合し、最も適切な治療を行う。⑤ 病の深い意味に気づき自己実現をめざす
病気や障害、老い、死といったものを単に否定的にとらえるのでなく、むしろその深い意味に気づき、生と死のプロセスの中で、より深い充足感のある自己実現をたえずめざしていく。
ここでは、①で、ヒトのあり方として、「からだ」と「こころ」の他に「気」「霊性」みたいなものがちりばめられています。ヒトを構成する要素はいろいろあるらしいです。
ここの、④にある「さまざまな治療法を選択・統合し、もっとも適切な治療を…」という文章が良い感じです。先日わたしが書いた「折衷」という思想そのものにも見えます。
実際的なな議論をするならば、理屈はどうであれ、それらをうまいこと折衷して、それぞれの治療法が同居できるのかどうか?お互いの組み合わせに無理はないのだろうか?というような現実対応の話をしてゆかねばなりません。
宗教的な救済と、現実的な救済の価値観における葛藤というのは、しばしば出現します。
そうした葛藤の中でも有名な話題に、たとえば「宗教的な理由で輸血を拒む方」というものがあります。
彼らの思想の中では、他者の血を自分の身体に入れることが禁じられています。その禁をおかしたら、どうなるのか…?みたいな話は具体的に聞いたことはありませんが、しばしば、手術の時に輸血を行うのかどうか、とか、救急でどうするのか、みたいな問題がでてきます。
宗教の戒律や禁忌をどこまで尊重するのか?という話になると、これも本当にバリエーションがあります。たとえばイスラム教徒は豚肉を食べてはならない、という戒律がありますが、「食べてしまってもごめんなさいしたら大丈夫」とか「他に食べるものが無かったときには仕方ないのだ」という「抜け道」を認めておられる方もいらっしゃるらしいです。宗派などによってその温度差があるようで、厳格な方から、わりと緩い方まで様々です。
そういえば、イスラム教では女性がスカーフを身につけることが求められますが、そのスカーフについてもいろいろあるようです。
このように聖典クルアーンには“美しいところを見せないように”とあるだけで、神(アッラー)は具体的に髪の毛をスカーフで覆うよう命じているわけではない。
https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2016/05/post-315.html
解釈はひとの数ほど出てきそうですよねえ…。時代によっても、文化によっても異なりそうです。
…とまあ、宗教議論は措いておいて、と言いたいところですが、臨床における診療も、どこか宗教…とまでは言いませんが、ある種の「信仰」によって成立している部分があるのではないか、と思います。
信仰、っていうと、極端な話になりますが、「おおきな前提」とでもいうものでしょうか。たとえばアドラー心理学の中にある「共同体感覚」というのは、その前提と言えるものです。
ひょっとすると、「漢方薬を内服すればひとは元気になってゆく」という考え方も「おおきな前提」のひとつなのかもしれません。
漢方の理論の中にある五臓論というのも、現場で使っていて、それほど大きな破綻が無い、という意味では現実的な審級を受けていると言えますが、その理論そのものはどこか「前提条件」的なものになっていると言えるのでしょう。
ホリスティック医学では「自然治癒力」という言葉を前提に掲げていますし、調和状態を健康の基準に挙げておられます。
この文章には書かれていませんが、それ以外の、言語化されていない前提、というのもありそうです。
こうした前提と、臨床が、うまいこと矛盾や衝突を引き起こさない形で成立すれば良いと思いますが、場合によってはズレることだってあります。
「こうであるべきなのに、現実はそうなっていない!」みたいな苦しみが出てくることだってありそうです。
あるいは、こちらの理論と、あちらの理論が衝突する…まあ理論はともかく、実践の方で衝突するなら、どちらを取るか、選ばなければなりません。
そのあたり、折衷主義でやっていると、現実対応は現実対応で…となっていきますが、日々悩むこともあります。思想としてはあまり美しくありませんし、中途半端になりがちなのですが、わたしはそんなところで日々を過ごしております。