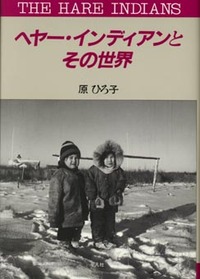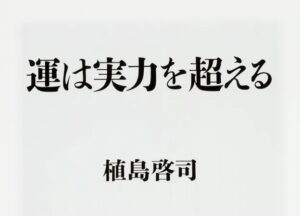マルバツ式テストの影響

この表紙デザインには、甲野善紀氏が、愕然とされたのだ、という話を聞きました。
マルバツ式ではなくて…という議論をしている本の表紙にマルバツ式…という矛盾です。
以前も国語の教科書に載っている文章について書いたことがあります。
今日もまた、別の国語の教科書に載っていた文章の話からはじまります。印象的なほどに心に残っている文章です。
「道ばたで、きれいな花が咲いているのを見つけたとき、あなたはどうしますか?」という問いに、娘は「ずっと、見つめている」と答えたのでした。
そして、その答えを、笑われます。
「マルかバツかでいうなら、この答えはバツよ。この問いは、たとえば「写真を撮る」とか、「押し花にする」とかそういう行動を選択させるものなのだから…」
テストのマルが大好きで、バツはいけないものだ、と思っている娘は、折角書いた素敵な答えを消してしまいました…(にしむらお得意の、うろ覚えのテキストの再現)
そんな文章を読ませて「マルかバツか」の試験問題に出してくる、という教育の矛盾を、その時にわたしがきっちり言語化できたかどうか、は定かではありませんが、物事を「マルかバツか」で査定する、ということについて、鋭く指摘したこの文章が、どこかに突き刺さったまま、今でも覚えているくらいには、印象的なテキストだったのだと思います。
最近の中学生や高校生は、試験の範囲、というのが、かなり明確に呈示されるのだそうです。
そういえば、昔、英検を受ける時に、こどもが大騒ぎしたのを思い出しました。「中学校1年生程度、って書いてある範囲なのに、知らない英単語が出てきている!」というのが、その時の言い分だったように記憶しています。
「〜程度」っていうのは、おおよそはそうであっても、まあ、知らない英単語も出てくるよねえ。なんなら、試験本番までに出てきて、既知の単語になっていくんだったら良いんじゃない?くらいの意識だったのですが、こどもにはそれが許せなかった?らしいです。
人生の中で、そんなにかっちりきっちり、試験範囲が決まっていることなんて、ほとんど無いわけでさ。そんなに目くじら立ててどうするのさ…?と思ったものでした。
それからしばらくした頃に、ご縁があって、大学生さんたちに講義をする機会を頂きました。
医療系の学生さんたちに、産婦人科関係の話をするのですが、まあ、講義の内容は多岐にわたります。教科書が3冊。授業のコマ数は8コマ。なかなか全部を喋るわけにもいかない…というジレンマの中に、それでも臨床の課題を実感してもらおうとして、いろいろなケースの話をしたり、「あなたが…」という仮定の話をしたりしたものでした。
学生さんたちの反応は、極めて寂しいもので、「雑談は良いからはよ授業してください」的なコメントをたくさんもらいました。
質問ありますか?と尋ねて、なにかあった…と思うと「それは試験の範囲に入りますか?」とか、「試験問題はどのような問題になりますか?」とか、あるいは「この小テストのここ、わたしの回答は不正解になっているのですが…?」とか。もう、テストのことと、点数のことだけでした。
あなたがた、現場に出てから、患者さんに、なにか尋ねられた時に「習っていないのでわかりません」って返事するわけ…?
…って思いながら、どのような問題でも、いったん、それを引き受けて、自分で考えること、って大事なんじゃないの?って言い続けてきた、つもりでした。
そういう行動は、コスパが悪い、わけです。
試験の点数に影響しないなら、勉強しない、というのが、かしこいやり方なんだそうです。
うーん…
と、考え込んでしまったわけですが、数年、こういうことをやっている間に、ふと、気づいてしまったことがあったのです。
専門領域のお医者さんが、「異常無いですね」とか、「それはウチの科の範囲じゃないです」とか、そういう返事をされている時。これって、つまり「わたしの試験範囲の話じゃない」って言っているようなものなんですよねえ…。
つまり、医者であっても、「自分の勉強したことの範囲外だ」というものは「知らない」「わからない」と言う。もちろん、自分が知らないことを、知っているかのように答えるより、謙虚に知らないことを告白する方が、だんぜん誠意ある行動です。
とはいえ、そこで「知らない」の先に「なので、考えない」という話になってしまうと、相談した側としては、突き放された気分になるわけです。
にんげん、生きていたら「答えの無い問い」なんていうものに、いくらでも遭遇するわけです。それをどうするのか?っていうのは、おひとり、おひとりの、個別の課題ですが、そこを支える、というのも援助職の仕事なのではないか、と、そのように思いながら、日々四苦八苦しているところです。