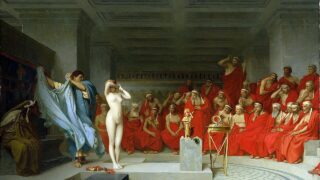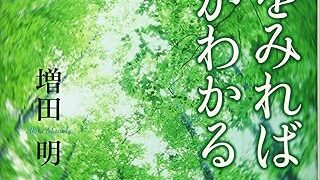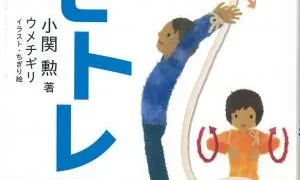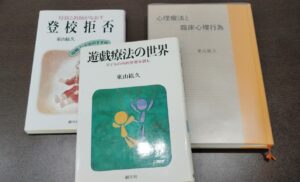全人的医療ということば

先日、漢方の講演会を聞きに行ってきました。いろいろと勉強になったのですが、なかでも、講師の先生が「全人的医療」ということをおっしゃっていたのが印象に残りました。
「病気をみているんじゃない。病人をみるのだ」みたいな文章はずいぶんと前からあります。そのような医療をしてゆくことを、理想とする…というのも、格好良いことなのかもしれません。
ところで、では、具体的に「全人的」というのは、どういう状況を指さしているのか…?って話になると、これがちょっと難しい。
しばしば言われるのは「心身両面を」という表現になっているようですが、身体と心のことのそれぞれについて診療していたら、即座に「全人的」と言えるのか?という問いにみなさん、どうお答えになるでしょうか。
へそ曲がりなにしむらは、ふと考えてしまいました。
「全人的医療を行う、ってことが、無条件に『良い』って言ってしまっても良いの?」
まあ、まずは全人的医療の定義から、なのかもしれません。あるいは良い悪いの判定を、誰がどこで行うのか、という話から、なのかもしれません。
ボディートークの師匠である、増田明氏は、にんげんの存在を「あたま」「こころ」「からだ」の3つの要素に整理して呈示していました。全人的、というのを、彼の言葉を借りるなら、「あたまも、こころも、からだも丸ごと」というような意味になるでしょうか。
昔、学生の時に、大学病院の関連施設に実習という形で見学に訪れることがありました。天理市には「天理よろず相談所病院」という名称の施設があります。
まるごとお困りごとの相談をします、という旗をかかげた、この施設は、もともと天理教の「よろず相談所」が母体になっているようです。
身体と心と生活に目を向け、「病(やまい)だけでなく、病(や)む人そのものに向かい合う」という“全人的”取り組みを、80年以上も前から続けて来ました。
と、法人についてのところで書いておられますので、自負があるのでしょう。
ところで。にしむらの文章にしばしばあることなのですが、いきなり話が飛びます。
高校受験とか、大学受験っていうのがありますよねえ。昔は試験一発勝負、的なものが多かったようですが、最近はアドミッションオフィス方式(AO入試)などというものもずいぶんと増えて来たようです。
筆記試験だけではわたしの良さは伝わらない!って思っておられる方も結構あるのだとか、そういう話をSNSなどで見聞きしますが、とある指摘が、わたしに突き刺さりました。
それは「筆記試験だけで不合格なら、まだ勉強が足りなかったとか、学力だけの問題だ、ということで話を済ませることができるけれど、全人的な評価を受けて、それで不合格、ってなったら、あなたは良いところ無し、ってことになるんじゃないの?」というような文章でした。(具体的な文章を、いつごろどこで見たのかを覚えていないので、意訳です)
試験のような「査定される」場面において、それを肯定的に受け止めてもらえるなら、全人的であっても良いのかもしれませんが、何らかの否定的な判定を受けるにあたって「全人的に判定して…」ということになると、逃げ場がなくなりそうです。
そんな追い詰め方しなくても…って言いたくなるでしょう。
医療においても、似たようなことが起こる可能性はあります。
全人的に医療を行う、ということが、査定であったり、あるいは本人のあり方へのダメだしであったりするような、ネガティブな形になるのであれば、逃げ場がなくなるような、きついモノになりかねません。
査定されるものは、自分から離れたものだけであってほしい、と、気の弱いわたしはそんな風に考えてしまいます。
その上で、全人的、という医療をどのように考えるのか…?これは本当にちょっと難しい話になりそうです。
長くなりましたので、続きはまた今度…(と言いながら、結論を先延ばしにする時間稼ぎだったりします)。