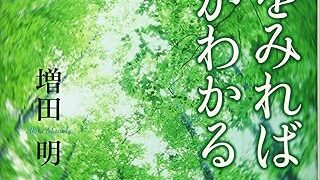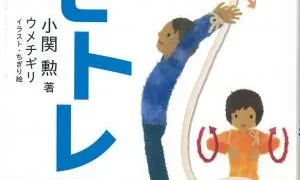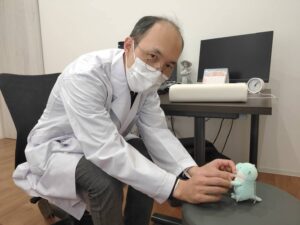古いこと、新しいこと

学問の世界では、分野によって、時間の感覚がずいぶんと違うらしいです。
「最近のこと」という表現があったときに、たとえば植物学の世界では、それは一千万年くらいを指しているらしい、というツイートがありました。
ツイート主の方は、中国や日本の古典をなさっているらしく、ご自身の専門領域では、500年くらいは「最近」のことなのだそうです。お隣におられた社会学がご専門の方の「最近」は「ここ10年くらい?」って話らしいです。
最近と言っても、本当に文脈によってスケールが違うものなんですねぇ。
「最近の若者は…」って表現で使われる「最近」って、いつ頃でしょうか?さすがに一千万年ってことはなさそうですけれど。
ところで。古代ローマの遺跡にも「近頃の若者は云々」って年寄りの愚痴めいたことが落書きされているんだそうです。落書きだから、もっと現代に近い方が書いたのか…?とも思ってしまいますが、古代ローマ時代のお年寄り?のボヤキのようです。
いつの時代も…と、ここで極端な一般化をすると、それは学問としては正確ではないのかもしれませんが…わりと変わらず、年かさの方が若者に苦言を呈する、あるいは、こっそりと愚痴をこぼす、ということがあったのかもしれません。
日本では、その逆の、年寄を揶揄する表現として「明治生まれの石頭」っていうのがありました。明治生まれがまだカクシャクとしていた時代の話だと思います。
ところで、さらにさかのぼると、「天保生まれの石頭」という表現もあったそうです。天保っていうのは、江戸末期の元号ですから、まあ、ご一新まえに生まれている…年寄りが、やっぱり頭がかたい、っていう愚痴やボヤキもあったのかもしれません。
ご一新、と書きましたが、こういう表現も、もうあまり使わなくなった気がします。最近の表現で言うなら、明治維新、ですね。その時代を見てきたわけではありませんが、文明開化だなんだと言って、古いものを否定した結果、「大人になるためにはどうしたらよいのか」という、人類社会を保つための智慧を喪失してしまったのではないか、と思います。
そういう明治時代に生まれ育った人たちが、今度は太平洋戦争と米国の占領統治を経て、昭和の時代には、子どもたち世代から再び否定されています。因果が繰り返されるということなのか、たまたま歴史の巡り合わせだったのか…。米国は、太平洋戦争の終結調印のときに、江戸時代に掲げていた国旗をもってやって来たと聞いたこともあります。歴史は繰り返す、というやつなのでしょうか…。
明治のご一新も、昭和の民主主義国家も、今までの思想の多くを「ダメなもの」だったのだ、という形で否定するわけで、特に大人が否定されるわけですから、近代において日本という社会は、立て続けに2回「大人になるためにはどうしたらよいのか」という智慧を喪失した、と言うことができます。
そういえば、ニュータウンというものも、その戦後民主主義の価値観で育った世代が選び取った、核家族と、お互いのプライバシーを大切にする構造ですね。
さて。動物の研究をしている分野で「ネオテニー」と呼ばれる現象があります。幼形成熟と翻訳されていますが、「動物が幼生形のままで繁殖できる状態になる現象」と説明されています。見た目は幼い、けれど、生殖は可能になる、という選択肢を選んで進化してきた種族がいる、ということのようですが、ヒトもネオテニーなのじゃないか、っていう問題提起をされることがしばしばあります。
幼く見える、あるいは幼い状態であり続けることが、生存や繁殖に有利だった、という世界線があるのでしょう。
動物の研究をされている方の話によると、必ずしもヒトに限った話ではなさそうですが、集団生活を送るヒトという種族は、文化や文明というものを発展させてきました。もともと、生物が次の世代に伝えるもの、というのは、生物学的な情報…つまり遺伝子やそれに関連する情報…がほとんど全てだったのですが、文化・文明の発展とともに、ヒトは「言葉」を発明し、これを用いてわたしたちの外側の情報を、外側の情報として伝えることができるようになりました。
こうした文化・文明を、生物学的な情報とともに引き継いで、次世代に伝えることが、ヒトとしての生存に有効だ、と、きっとそのような判断が下ったのだろうと思います。
とはいえ、外部化された文化・文明の情報は、ヒトという生物の速度を超えて変容し、情報は情報を呼び込んで複雑化していきました。「負うた子に教えられ」という俚諺がありますが、世代更新よりも断然早い情報の更新に、若者はなんとか適応しているようにも見えますが、年齢を重ねてくると、そのような柔軟性が喪われていることもしばしばです。
時代が変化してゆく、となると、若者は、老人を侮ります。「石頭」という表現は、その典型的なものなのかもしれません。
そして、若さといきおいで、老人のあり方を否定した結果…わたしたちはどこにもたどり着けず、幼弱なあり方のままで迷子になっている、ようにも見受けられます。
「古い価値観に戻るべし!」などという主張をされる方もいらっしゃるでしょうが、なかなか現実的とは言えないわけで、本当に新しい価値観が求められているのかもしれません。