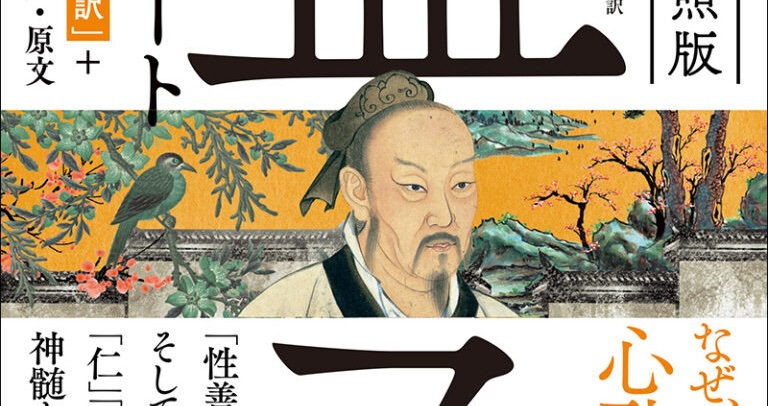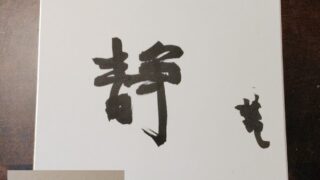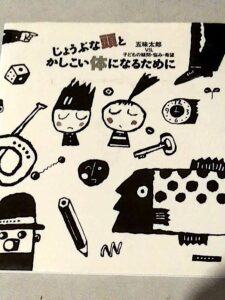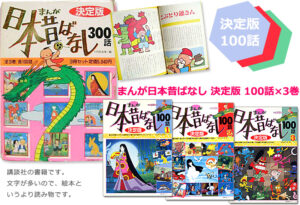君子の話

君子に三楽あり、っていうことばがあったよなあ…と、その言葉を引っ張ってきて、先日、ブログ1本を書いたところでした。
このブログ記事を書くときに、君子に…と検索をかけたら、グーグル先生、候補を挙げてくれました。
「君子に三楽あり」「君子に三畏あり」「君子に三戒あり」
他にも「君子に二言なし」「君子の六芸」「君子に九思あり」
いやあびっくり。君子って言われると、いろいろ数えねばならないものがあるらしいですねえ。
それぞれ、ご興味がありましたら(無いって)グーグル先生にお尋ねくださいませ。
…さて。くんし、くんし、って言ってましたが、そういえば、漢方の処方にも「君子」という名前の入った処方があります。
「四君子湯」というのと「六君子湯」というのが、それです。
漢方薬の処方内容を分析して見る時に、構成されている生薬を「君薬」「臣薬」「佐使薬」という形で分類して考える、という話があります。
四君子湯というのは、もっぱらこの「君薬」になれるような生薬を四種類並べてきた、というような意味合いになるでしょうか。
人参(高麗人参)、朮(白朮あるいは蒼朮…オケラの根っこ)、伏苓(マツホドと呼ばれるキノコ)、甘草、というのが四つの君子、として挙げられています。
四君子湯は、ただし、この四つだけではなくて、生姜(ショウガの乾燥させたもの)と大棗(ナツメの実)とが加えられて、六生薬で構成される処方です。
六君子湯は、この四君子湯に陳皮(ミカンの皮を乾かしたもの)と半夏(サトイモの仲間の根茎)とが追加された処方になります。
陳皮半夏(チンピハンゲ)と並べて言いますが、このふたつの生薬を含むものに「二陳湯」というのもあります。胃腸を動かして余分な水を外に出す、というような意味合いが強い生薬です。
日本は、中国本土に比べて、湿気が強いことと、おそらく、日本人の胃腸が比較的弱いことから、陳皮半夏を加えた方が良い方が多いのだろうと思います。
なので、四君子湯よりも六君子湯が用いられることが多いですし、抑肝散、という処方が中国で生まれて、日本に伝わった後、抑肝散加陳皮半夏、という処方が日本で発生しました。
もうひとつ脱線すると、陳皮は温州ミカンの皮を乾燥させたものですが、「陳」の字は「古い」ということを意味します。乾燥させて、長期間保存しておいたものの方が良品として扱われる、ということで古いものが良いとされる「六陳」…六種類の生薬…と、新しいものが良いとされる「八新」…八種類の生薬…がある、などと言われます。陳皮も半夏も、六陳の方に含まれています。
陳皮は、脳神経に効果がある、という話があり、認知症の症状改善に、陳皮が有効なのではないか、という話もあります。
必ずしも漢方薬でなくても、柑橘系のアロマなどでも良いのかも知れません。
ミカンの皮は、たいていは剥いたあと、生ゴミになっていましたが、こういう話を考えると、あれ、とっておいて、乾燥させたら良かったんじゃないか…?なんて考えてしまいます。
まあ、手間がかかりますし、うっかりカビなど生やしてしまうと目も当てられませんから、ご家庭で自家製されるときにはくれぐれもご注意くださいませ。
ちなみに、君子の対義語は「小人」ということになっているようです。
しょうじんかんきょしてふぜんをなす(小人閑居して不善を為す)、なんていうのは、君子との対比としてはわかりやすい箴言なのかもしれません。
君子と小人の違いを、わたしの師匠は「才能」と「人徳」のバランスで説明しておられました。曰く、「人徳」が「才能」に勝つのが、君子。「才能」が「人徳」を超えてしまっているのを小人と呼ぶのだそうです。
才気走ると、なんとなく偉くなったような気がしますが、それはどこまで行っても「小人」なのだ、と言われると、身が引き締まります。「才」が大きければ大きいほど、小人を卒業するためには、人徳を涵養せねばなりません。
山椒の実は小粒でもぴりりと辛い、という俚諺もありますから、小さくて何が悪い!って言い方もできますが、小人の「小さい」はそういう意味ではなさそうですよねえ…。慢心せずに、徳を積み上げてゆきたいものです。