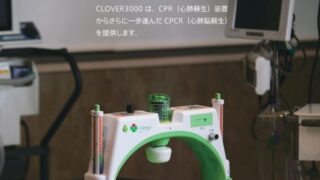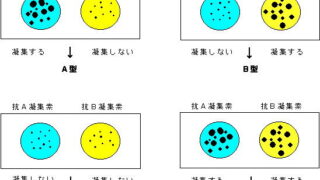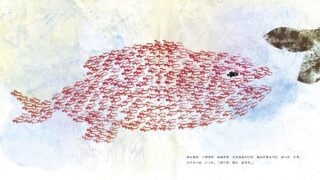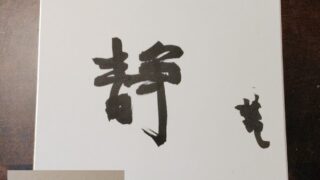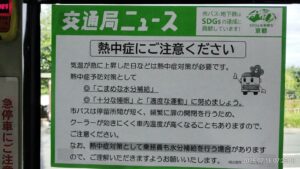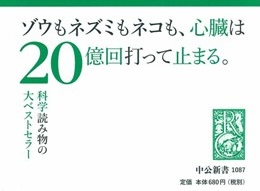四苦八苦

昨年の8月末から書き始めた「院長のブログ」ですが、だんだん書くことがなくなってきて、ブログの話題を引っ張り出すのに四苦八苦しています。
ところで、四苦八苦、って言葉も仏教の用語でしたが、ご存知でしたでしょうか?
四苦とは「生・老・病・死」の四つを指します。
この話はお釈迦様の「四門出遊」というエピソードにも語られるところです。
お釈迦様が出家されるきっかけになった話として語られています。
それぞれ別の日の話ですが、城の門から外に出たところで、順番に老人と、病人と、そして、葬送の行列とに、それぞれ出会います。
ひとの苦しみ、というものを深く考え込んだところで、最後に出家者に出会い、彼が心を穏やかにするべく修行している、というのを聞いて、お釈迦様も、ご自身の進路をお決めになられた、という話でした。
このエピソードでは「生」が苦である、という話は出てきませんが…。
さて四苦八苦のうち、残りの四つは、ちょっと面倒くさいです。
ウィキペディア「四苦八苦」には
・愛別離苦(あいべつりく):愛する人と別れる(生別・死別)苦しみ
・怨憎会苦(おんぞうえく):怨み、憎んでいる相手に出会う苦しみ
・求不得苦(ぐふとくく):求めるものが思ったように得られない苦しみ
・五取蘊苦(ごしゅうんく):ひとの心と身体が思ったようにならない苦しみ
と並んでいます。最後のやつはわたしは五蘊盛苦(ごうんじょうく):その他もろもろの苦しみ、と記憶していましたが、いろいろな表現があるようです。
この四苦八苦を4×9+8×9ということで、煩悩の数が108に計上されるようになった、ということで、わたしは聞きました。うん?苦を9に読み替えるのって、中国とか日本に来てからのことなんでしょうか?とか、四苦八苦のうち、四苦分は計算上2回数え上げていることになるのですが…?とか、細かいことは言ってはいけません。
実際には108を数える別の方法もいくつかあるみたいですので、まあ、四苦八苦で108、という話は、面倒くさい理屈を省略するための方便だったのかもしれません。
年末になると、除夜の鐘、というのを108回衝くのだ、という話になっていますが、この煩悩の数だけ、鐘を鳴らすことで、その煩悩をはらっていくのだ、ということのようです。
なお、仏教では、愛する、ということも「執着」のひとつである、として、戒めることになっています。
お釈迦様が、うまれた息子に「ラーフラ」と名付けたそうですが、一説によると、これは、お釈迦様が肉親への愛情を持つことで、出家を邪魔することになってしまうから…だったそうです。
お釈迦様ですら、家族への愛情を持っていて、それは、ひとつの執着になる、というエピソードになっています。
なかなか一般人に、お釈迦様の心境を超えて、愛ゆえの執着を手放しなさい、というのは、難しいことなのかもしれません。
さて。抹香くさい文章が続きますが、せっかくなので、お釈迦様の教えで、この苦しみにどう対処したものか…というあたりをご紹介しておきます。
四諦(したい)というのが、その苦しみに対する答えになります。四、ですから、具体的な内容は四つに分類されます。
・苦諦(くたい) - 迷いのこの世は一切が苦(ドゥッカ)であるという真実。
・集諦(じったい) - 苦の原因は煩悩・妄執、求めて飽かない愛執であるという真実。
・滅諦(めったい) - 苦の原因の滅という真実。無常の世を超え、執着を断つことが、苦しみを滅した悟りの境地であるということ。
・道諦(どうたい) - 悟りに導く実践という真実。悟りに至るためには八正道によるべきであるということ。
つまり「にんげんとして生きている、ってことの中に、いろいろな思いがこびりつくと苦しくなるから、それを手放してゆこうね」ということになります。
この、いろいろな思い、っていうのが、やっぱり、曲者で、この思いがあるからこそ、日々を生きることに繋がる部分もあります。一概に全部を捨て去って…という極端な話に進むわけでもありません。
わたしのブログも、書くのがしんどいから!ってなったら、さっさと諦めて、更新を止めたら、このしんどさは無くなるのかも知れませんが、まああまり気負わず、ぼちぼちの更新でまいります。