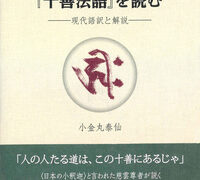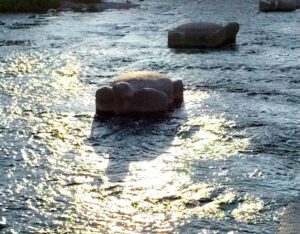四里四方

四角四面…ではありませんが。
四里四方。
そんな名前のお店もあったようですが…「四里四方に病なし」という俚諺があります。
場合によっては「三里四方」という言い方もされたのだそうです。
これは「地産地消」の生産範囲を具体的に絞ったもの言いのような気がします。
食養生関連では、「身土不二」という言い方をしたりします。
これはもともとは仏教の用語にあったものを、意味を転用し、ぜんぜん別の意味で使っているようです。
Wikipediaによると、
身土不二
(しんどふに)仏教用語。「身」(今までの行為の結果=正報)と、「土」(身がよりどころにしている環境=依報)は切り離せない、という意味。
(しんどふじ)食養運動のスローガン。「地元の旬の食品や伝統食が身体に良い。」という意味で、大正時代に「食養会」が創作した。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%9C%9F%E4%B8%8D%E4%BA%8C
…と、記載がありました。石塚左玄という、明治の食養生の大家が言い始めたようで、その後、石塚の流れをくむ、桜沢如一(マクロビオティックの提唱者)がその言葉を使って、日本にひろがったようです。
たとえば、暑い熱帯で摂れる作物は、身体を冷やす働きがある、とされています。なので、日本(だいぶ熱帯化してきている様相はありますが…)の夏はともかく、寒い季節に、熱帯から輸入された果物を大量に食べる、などすると、身体が冷えて調子を崩す、とか。
そういえば、日本人は海苔を食べますが、これを消化できる酵素を持っているのは日本人だけだ、という話を聞いたこともあります。
消化できる酵素だったか、消化できる腸内細菌だったか、ちょっと記憶があやふやですが…。
穀物菜食に憧れて、日本にやってきたけれど、腸内細菌がどうしてもあわなくて、穀物菜食だとお腹を壊してしまう、という外国人のエピソードを読んだこともあります。
思想と、今までの食生活との差というのもあるのかもしれません。
ヒトが、健康に生きるにあたって、地元の作物を食べているのが一番良い、という結論は、長距離を移動する、とか、大容量の輸送手段を持つ、とか、そういう文明の利器が出現するまでのことを考えると、きわめて合理的ではあります。
わざわざ遠くから運んできたものを食べなければ健康を維持できない、となると、そんな種を維持するコストが高くなりすぎますので…。
ところで、ヒトは「脂肪」「糖分」「塩分」がとても大好きです。これらは、生物進化の時代にとても貴重なものだったのでしょう。これらを摂取すると、脳の報酬系が極めて鋭敏に反応します。
最近の問題は、ヒトが文明の利器を駆使した結果、これらを過剰に摂取している、という点にあります。極端に制限しすぎるのも問題ではありますが、げんじょう、日本人は飽食気味です。これらの摂取量がだんぜん、必要最小限を超えています。滅多に手に入らない時代であれば、たまに口に入る時に、多少多めに食べておいても、まあ、それほど大きな影響にはなりませんが、毎日多めに…となると、いろいろと不具合が出てきます。
ヒトの身体の「ちょうど良いを見つける才能」というのは、まあ、ですから、文明の利器が酷使される前の状況から変わっていないのかもしれません。今の世の中では、だいぶ雰囲気が変わってしまいました。
甘いもの、に対する渇望も似ている気がしますし、作物についても、ずいぶんと品種改良が進みました。
本当に身土不二であれば良いのか、とか四里四方であれば良いのか、という話になると、すでに文明の影響で、距離だけじゃない意味合いで、わたしたちは、ずいぶんと遠くに来てしまったのかもしれません。
とはいえ、やはり、地のものをいただく、というのは、とても大事なことです。旬の野菜をいただく、ということも必要なことなのだろうと思います。なるべく、季節のものを、その季節にいただく、ということが、健康に生きる上では大事なことなのかも知れません。
…と言いながら、ヒトはいろいろと工夫をしていますから、いちがいにそれだけを墨守する、というのも話が違いますよねえ。たとえば、お米。
お米が採取できる季節は、秋の1回だけです。季節のものをいただく、ということを厳密に守るなら、秋口以外はお米は食べられません…みたいな話になってきたりしそうですが、そうは言いません。
たとえば、漢方の薬。これも日本国内だけで製造できるものではありません。
なので、四里四方が絶対的な基準でもないわけです。が、一つの思想として、やはり季節のものをいただく、ということ、近くのものをいただく、ということは、わりと良い基準になっているようには思います。
なぜ、地元の、季節のものが良いのか?というのは、ずいぶんと謎の多い話ではありますが、長くなりましたので、これはまたいずれどこかで。