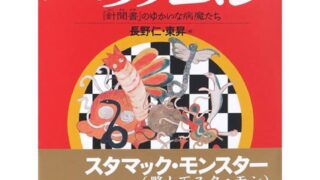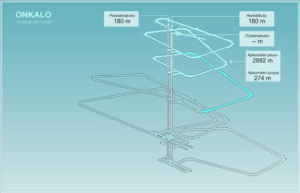因果関係って難しい

原因と結果、ってわたしたちはわりと簡単に口にします。
たとえば、高いところまで石を持ち上げて、その支えを取ると、石は落ちていきます。
「原因」は石から支えを取ったこと、で、「結果」として石は落下するわけです。
あるいは、「原因」は石と地球の質量で、「結果」としてそれらが引力を介して衝突する、という説明もできます。
単純な物理現象の場合は、原因と結果がわりと明確で、だいたいは、原因となる物事が発生して、その後、わりと時間的には近いところで、結果が生じる、ということになります。
計算はややこしくなりますが、丁寧に計算を重ねると、万有引力と、惑星の質量・そして太陽の質量と、それぞれの位置関係から、惑星の運行も予測できたりするらしいです。
小さい方で言うなら、原子核がどうこう、というところも物理現象として研究できるらしいです。
ところが、こと、ヒトのことになると、物理現象「だけ」というわけにはいかなくなります。
とくに、「こころ」に関係してくる話題になると、因果関係があやふやになってくることもしばしばあります。
以前も書きましたが、ひとの感情というものを、「結果」としてとらえる考え方が一般的ではありますが、わたしの学んだアドラー心理学では、むしろ「原因」に近いところに感情を置きます。つまり、自分自身の思ったように世界を変化させたい、という欲動が、その感情を呼び起こし、その感情を発現させることで、世界を変化させようとする、という動きが、ひとのこころにはあるのです。
いや、不快なことがあるから、泣いたり、怒ったりするんでしょ?っていう方もあると思います。
ですが、赤ちゃんでさえ、「聞き届けるひとが居ない」と知ったところでは泣かないんです。
たとえば、聴覚障害のお母さんに育てられている赤ちゃんは、お母さんが自分の方を見た、ということを確認してから泣き始めるのだそうです。
だから、やっぱり「聞き届けるひとが居る」ということと、そのひとに何かを期待する、ということが重なったところに、感情が発生している、ということになります。
オムツが濡れているとか、お腹が減った、というのが原因…の「ひとつ」にはなるのでしょうが、それだけが理由で泣いているわけではない、ということです。
因果関係の話に戻ります。
わたしが医学部の学生だった頃に、消化器内科の教授が「肝炎ウイルスの慢性的な感染が、肝細胞癌の原因である」と講義しました。
当時、まだ複雑な因果関係を納得していなかったわたしは、教授に食ってかかったのでした。「あ、コイツに説明するの、ちょっと無理だな…」的な、面倒くさいというか、ちょっと絶望したような教授の表情を今でも覚えています。
いや、だって、肝炎ウイルスのキャリアの方でも、皆がみな、肝細胞癌を発症されているわけじゃないですし…。
そういう言い方をするなら、喫煙が肺癌を引き起こす一因になっている、という言い方も出来るのですが、こちらも、統計的な処理を完遂するまでは、気づかれなかった、ということが『がん--4000年の歴史--』には描写されています。
なるほど。因果関係がありそう、って話は、こうやって統計的な計算をするのね…という話になります。
こういう比較をするには、かなりの数の人たちを観察しなければなりませんし、比較する以外の条件をなるべく揃えねばなりません。
フレンチパラドックス、という言葉をご存知でしょうか?
一般的には飽和脂肪酸を含む食事をしていたり、喫煙者が多かったりすると、心筋梗塞をおこす率が高まる、とされているのですが、フランスでは、心臓疾患の発生率がそれほど高くない、ということで、フランス人の謎、とされていました。その後、赤ワインを内服していると、心筋梗塞を含めた心臓疾患の発生率が下がる、という研究結果が出ています。
ところが、アルコールの摂取が健康に良い、という話はどんどん減りつつあります。詳しい話を調べると、実は、ワインの摂取量は、ワイン接種者の経済的な裕福さとの関係が密接であり、「ワインを摂取しているから」健康になっている、というのではなくて、「裕福な生活を送っているから」であった、ということが近年判明してきたのだそうです。
統計的な計算では関係がありそうな数字の中で、でも、実際に因果関係が無いもの、という因子を「交絡因子」と呼びます。
たとえば、夏になると、暑くなりますから、氷菓の消費量は増えます。
また、暑いですから、水難事故の件数も増えます。
暑さ、という因子をいったん横に置いて、見ないようにしておくと、氷菓の消費量の変動と、水難事故の件数とは、わりと似たような動き方をしているように見えます。
この2つだけを組み合わせて、「氷菓の消費量を減らせば、水難事故は減る!」という主張もできるかもしれません。
あるいは逆に、「氷菓の消費量を増やすには水難事故を増やせば良いのだ!」みたいな暴論も、数字のトリックとしては、言えてしまう可能性があります。
もちろん、そんなことはどちらもあり得ないわけですが。
相関がある、ということがすぐに、因果関係がある、ということにはなりません。結構このあたりを考えるのが大変だったりします。
わたしの師匠筋のとある方は、「因果関係」の因・果の間には「縁」があるのだ、だから、因・縁・果の関係で、縁がなければ、通常の因果の関係も成立しないのだ、とおっしゃっていました。
たとえば、インフルエンザのウイルス(因)が身体に入ったからといって、全てのひとがインフルエンザを発症する(果)というわけでもありません。そこには感染が起きる条件(縁)が必要なのだ、ということでした。
ひとの身体の異常についても、似たような話がいっぱいあります。
特定の食品を摂取していると、健康であるひとが多い、という話があったとして、じゃあそれを無理に摂取したら健康になれるのか?というのも難しい話だったりします。
体調の不良に対する治療も、単純に治療薬を使ったら元気になる、という単純な因果関係だけではありません。もちろん、わかりやすい因果関係が見えるくらいに、スッキリと治るのであれば、それはそれで有り難いことで、喜ばしいのですが、なかなかそういう経過だけではありません。
うまいこと、治癒に繋がるような縁を引っ張り出してきたいものだと思いますが、これも縁を上手に…というところにも単純な因果関係ではなかったりしますので、また難しい…というのが悩みどころです。