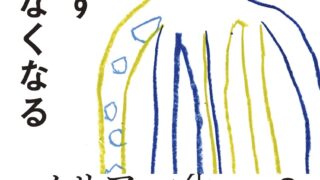変な生薬の話

先日、健康教室の時に、少し瘀血の話をしました。
駆瘀血作用をもつ生薬にも、いろいろあります。医療用のエキス製剤には採用されていない生薬として有名なもののひとつが「ヒル」です。生薬名は「水蛭(すいてつ)」と言います。
基源:ヒルド科(Hirudidae)のウマビルWhitmania pigra Whitman,チスイビルHirudo nipponica Whitman,チャイロビルWhitmania acranulata Whitmanを乾燥したもの
https://www.uchidawakanyaku.co.jp/kampo/tamatebako/shoyaku.html?page=227
ヒルは、血を吸うときに、吸い付いた場所の血液が固まらないような工夫を上手にしているのだそうです。地域や時代によっては、何らかの形で鬱血した場所に吸い付かせる…というような使い方もあったようです。
結構瘀血を動かす作用が強いようです。妊娠中の胎児も、ある意味で、血が凝ったもの、とされていますので、瘀血と似ています。強い駆瘀血を行うと、流産にいたる可能性がある、ということでこのヒルを用いることは禁忌になっています。
ヒルの話をしたら、駆瘀血作用のある生薬として、もうひとつ紹介したくなるものがあります。「シャチュウ」です。
基源:ゴキブリ科(Blattidae)のシナゴキブリ Eupolyphaga sinensis,またはマダラゴキブリ科サツマゴキブリOpisthoplatia orientalisの雌の成虫全体を乾燥したもの.
https://www.uchidawakanyaku.co.jp/kampo/tamatebako/shoyaku.html?page=256
ゴキブリ??って思いますよねえ。
一応、日本の台所などで嫌われているアレとは別の種類らしく、羽のない種類、ということになっているのだそうですが、それにしても…と二の足を踏む思いです。
そんな「シャチュウ」、富山の和漢診療部ではそれなりに処方されるのだ…とかいう話を聞いたことがあります。大学病院でゴキブリが処方される、ってどうなの?って思いますけれど、水蛭とあわせて、この動物性生薬、とてもよく効くのだとか。
ゲテモノ系で言うと、サソリを乾燥させた「全蠍」という生薬が入っている処方をみかけたこともあります。これも駆瘀血剤でした。ひょっとしたら、外骨格の生き物なら、なんでも良いのか(よくない)と勘違いしてしまいそうです。
念の為、としらべてみたら、全蠍は「熄風薬」に分類されるようで、麻痺とか痛みとか、半身不随、みたいなところで使うようでした。勘違いしていたようです。
日本で有名な動物性の生薬というと、「熊胆(ユウタン)」…クマの胆嚢・胆汁とか、「蟾酥(センソ)」…ガマのアブラ?とかっていうのが民間薬では使われていたようです。
あるいは「牛黄(ゴオウ)」というのが、牛の胆石だということで、このあたり、なかなか手に入りづらい生薬であるようですが、薬局の高い生薬製剤に含まれているという宣伝が出ていたりします。
鹿の角「鹿茸(ロクジョウ)」というのも、わりと有名な生薬です。奈良公園の鹿などは、角を切ってしまいますから、さぞかし薬の原料として有効活用されているのか…?と思いきや、その辺いろいろと難しいみたいですね。
漢方が好きだ、という話をしていたら、昔、同僚の先生が「こんなところに」と外科の学会誌を紹介してくださったことがありました。
健康のため、と野生の猪の胆嚢を入手して、その胆嚢の中の胆汁を自分で摂取していた方が、E型肝炎に感染された、という報告
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/57/11/57_606/_article/-char/ja
E型肝炎は野生の猪や鹿の内臓などから感染することが考えられていますが、健康のため、という思いで内服されていた胆汁からの感染、というのは、どうにもあべこべな話に感じられてしまいます。
医療用で用いられている動物性の原材料は、現在、ほとんどのものが、ウイルス感染を防ぐような形で精製されている…と言いたいところですが、血液製剤の一部ではやはりパルボウイルスなどが除去出来なかったりするようです。加熱してしまうと、タンパク質が変性して、目的とした作用が失われてしまう、などということもあり、悩ましいところです。
そういえば、胎盤、などというのも、薬の原材料として用いられるのでした。漢方では「紫河車(シカシャ)」という生薬として記録されています。現代日本では「プラセンタ」というほうがわかりやすいかもしれません。
これも現在はヒトの胎盤を使っていたり、豚や牛の胎盤を使っていたりするようで、ものによって異なります。注射薬は、いわゆる血液製剤と同じように、使った場合はその後、献血を避けていただくように、という話になっています。このあたり、防ぎきれない感染の連鎖を極力予防するように、ということで、ご理解ください。