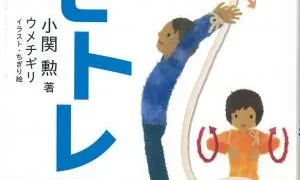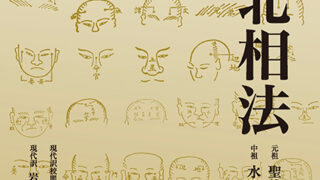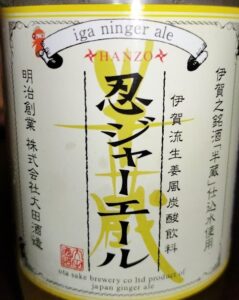妻と母の仲が悪いとき
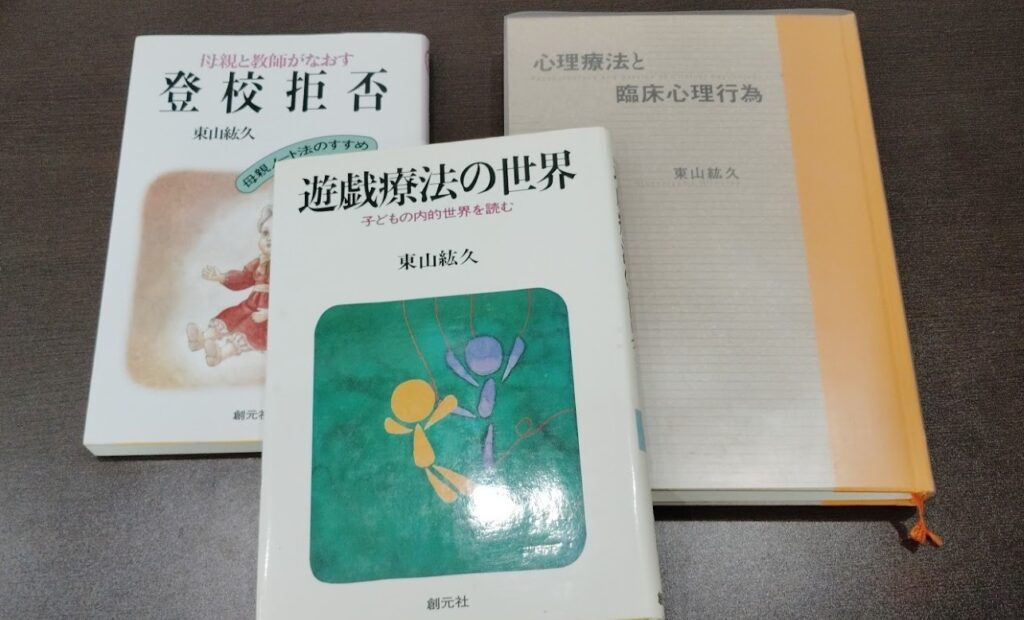
昨日に引き続いて、東山紘久先生の思い出話を、もうひとつ。
世の中には「嫁姑問題」というのがいろいろあります。で、その間に挟まれる(?)のが男性…「妻」の夫であり、「母」の息子である…になるのが世の常、かどうかは措いておいて、まあその男性がわりとシッカリしていると、嫁姑問題の波風が立ちにくいのだ…という話をしてくださっていました。
コツは「妻が、姑の文句を言ったら、うんうん、あなたが正しい!と全部肯定しておく」。間違っても「母にもははの事情があるのだから」などと反論してはいけない、ということでした。
なるほど?つまり妻の全面的な味方になる、っていうことですね?
…いいえ、違います。「母が、嫁の文句を言ったら、うんうん、その通り!と全部肯定しておく」という行動も一緒に行うのだそうです。
つまり、妻も母も、「自分がいちばん大事にされている」と実感出来るようにする、というのが大事なのだそうです。
ちょっと待ってください。2人の言い分にそれぞれ「あなたが正しい!」ってやりあってたら、2人が一緒に来たら、矛盾するんじゃないですか?
そうです。なので、2人いっぺんに来たら…
「逃げ出すのです!」
とはいえ、お互いに「自分がいちばん大事にされている」という感覚があれば、それぞれ、相手に対して、多少なり鷹揚になれるから、喧嘩が減るのだ…と、そういう話でした。
わたしは三人兄弟の真ん中で育ちましたので、母が兄弟喧嘩の仲裁をするときには、兄と喧嘩すれば「お兄さんを立てなさい」と言われ、弟と喧嘩すると「兄なのだから我慢しなさい」と言われ、わたし一人、ひたすら我慢させられているのか…と思っていました(3人に平等に叱っていた、と、これは母から証言を得ました。平等だったのでしょう。母の視点からは。お互いに叱られている場面は見えないように配慮していましたから、子どもには分かりませんでした)。
東山先生のこの話を聞いて、なるほど、逆だったのか!と膝を打ったものでした。
この話を伺った時に「先生…わたしは…」と自分の兄弟喧嘩の仲裁についての思いをやっと言語化でき、涙を流したのを、今でも覚えています。
先生は、やさしく、聞いてくださっていた…のだと思います。
一貫性のなさを、批判されるような話なのかもしれませんが、ひとの心についてのある種の真実がここにあるのだと思います。
だからこそ「ただしいことはたくさんある」わけです。
臨床というのは、そういう場所なのだろうと思っています。
だからこそ臨床の言葉は「賞味期限が短い」という話になるのでした。