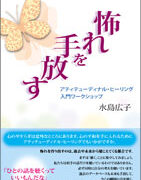推理小説のような

先日、漢方の勉強会がありました。
東京で開業されている、とある有名な先生がご講演される、ということで聞きに行ってきました。
とても興味深い話をいろいろされていて、へえええ。ってうなりながらお話を聞いてきたのでした。
お話を伺って、やっぱり、当たり前のことを、当たり前にやっていく、というのが大事なんだなあ、と、改めて心強く感じました。
そんなお話の中で、講師の先生は半ば謙遜もあってのことと思いますが、
「漢方薬で治しているんじゃなくて、口で治している」、と言われる
…と、そのようなことをおっしゃっていました。
とくに心の問題があって、それがストレスとして身体症状に影響を及ぼしている場合は、薬を使ってみたところで、それだけでは解決しないのだ、というのが持論の先生で、親子喧嘩の仲裁をされたり(喧嘩のストレスで症状が悪化するのでなるべく減らしてほしい…とお伝えされたのだとか)することもあったのだそうです。
そんな先生がおっしゃっていたのが、「ストレスの原因、っていうのがあるのだ」という話。
その根っこというか、中心点というか。
原因を突き止めて、それをなんとかすることで、ストレスが取っ払われて、症状が解消してゆくのだ…というお話でした。
あたかも、推理小説のように、患者さんの話を聞き取って、その中心点を突き詰めて行くのだそうです。
ほおお。
東京で名医として知られるその先生の話を聞きながら、わたしは、自分の診療を振り返ったのでした。
わたしは自分の診療の中で「推理」しているのだろうかしら…?
この答えは、わりとすんなり出ました。
わたしは「推理」していない。です。
じゃあ、わたしが臨床でやっているのは、推理じゃなかったら、なんなのか?って話ですよねえ。
それを、わたしは「物語を作る」ことだ、と思っています。
つまり、推理の対象になるような「問題のカギ」がどこかに実在としてある、というのではなくて、わたしと、患者さんとの間の共同幻想の中に、あたかも、「問題のカギがあるかのような」物語が形成されたなら、そのカギをなんとかすることで、問題が解決する、という。
ちょっと面倒くさい話ですよねえ。
西洋医学は、基礎研究が進んで、いろいろと詳しく分かるようになってきました。
なんとやらの分子がどこそこにくっついて…云々。
炎症を引き起こすなんたらがうんたらかんたら。
遺伝子のなにやらが、ほにゃららしてどうの…。
そういう「科学的な説明」は、どんどん細かい話が論文になり、次々できるようになってきました。
が、それは、にんげんの生活感覚とか実感からは、ずいぶんと離れてしまっている、というのも事実です。
漢方の説明は、そのぶん、かなり大雑把です。
でも、ある程度大雑把な、その漢方の説明のほうが、意外と実感に沿っている場合があります。
もちろん、これは「仮説」ですから、実際にその説明で出てきた「この処方が効く」というのも、じっさいに効くまでは、仮説です。「効くと思うから使ってみよう」というのが正確なところです。
この「物語をつくる」ということは、病気の説明だけには限りません。
昔、ちょっとだけ、タロットカードで占いをしようか…と思っていたころがありました。カードを何枚か拡げて、それらの意味をまとめ上げる形で、運勢を読むわけです。
こういうところで、「物語をつくる」という作業はとても重要な意味があります。
いらっしゃっている方と、共同の作業になるからこそ、そこだけで語られる物語がありますし、時々、そんな話をすると、それで、楽になられる方もあるようです。
東京の漢方の先生が推理されている、のは、それはそれでとても素晴らしい診療をなさっているのだろうと思います。
わたしは、ちょっとやっぱり、そんなに偉い先生のようにはいかない、というか、その先生とは別の、自分の道を辿ります、ということなんだろうな、と思ったので、こっそり書いておくことにしました。