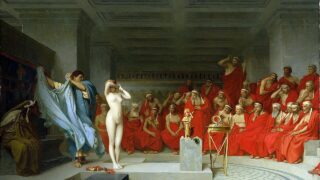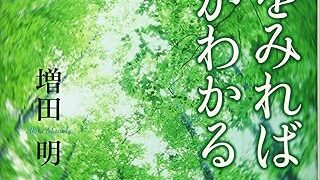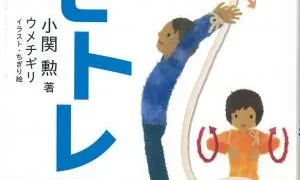治るってどういうこと

病気をした、怪我をした、という状態から「治る」という言葉を、わりと当たり前のように使うのですけれど、そうやってふんわり使っている「治る」って、究極的にはどういうことなのか?を真顔で考えるとけっこう難しいのです。
病気や怪我をした経験は、たいていの場合、記憶としてそのひとの中に残るわけです。それは「病気ないし怪我の影響」がそのひとの中に残存している、とも言えます。それを「治った」と称して良いのでしょうか?
いやそんなのは当たり前でしょう。跡形もなく治した、なんていう話はないわけで…と考えを続けているところで、ひとつ思い出した話があります。
野口整体の創始者、野口晴哉氏の話です。お子さんが小さい時に、ブランコに足を挟まれて、骨折されたのだそうです。野口家の創始者として、一切の医療行為を入れることを拒絶しておられたので、いかなる薬も、検査もお断り、というのを実践しておられるところでしたから、晴哉氏がおひとりで治療をなさって、それで治した、のだという話が残っているのですが、「折れた足」が、右足だったのか、左足だったのか、ということを、骨折をなさったご本人も含めて、誰も覚えていないのだそうです。
「子どもが足の骨を折って…」という話は時々、晴哉氏の講演でも言及されていた記録があるのだそうですが、そのいずれにも「みぎ」とも「ひだり」とも残っていない。
このくらい、徹底してその「記憶」や「記録」すらも消失させることができないと、「治る」とは言えないのかもしれません。
じゃあ、腰が痛くなった、とか、膝が動かなくなった、などの症状が出てきたのを「治す」っていったいどういうことか?って話になると、治しているとは言えないわけです。「そもそも治っていないんです」と整体の先生はおっしゃっていました。腰や膝を悪くしたとして、それが治ったわけではない。治ってはいないのだけれど、それを痛まないように使うことはできる。だから、痛まないような身体の使い方を覚えて、そう動くのが当たり前になれば、痛まない。そういう思想なのだそうです。
風邪についても、似たような思想を発揮しています。以前触れましたが、風邪を「治す」とは野口整体では書いていない。「経過させる」と書いてあるのです。
慢性の病気の場合は、「うまいこと付き合っていく」というスタンスもあったりします。
治療が必要なくなる状態のことを「治った」と呼ぶのであれば、それはそれで1つの定義です。そういえば、労災の「治癒」認定って、治療の効果が上がらなくなっている段階で下される判定になっていました。
わたしも一度その認定を受けましたが…。「まだまだ、もとの現場では働けないんですけれど…?」と質問したら、「たとえば、技能職の方が、片手を喪ったとして。その手は生えてこないですから、ある程度のところで、治療は終了になりますよね?それと一緒です」というお返事をいただきました。
幸いにして、わたしはその後、ふたたび臨床の現場に立つこともできるようになりましたが、当時はだいぶ目の前が暗くなったような気がします。
治療の効果が得られなくなった状態のことを労災の文脈では「治癒」と呼ぶのだと教えてもらいました。
そのあとは、症状と付き合っていくしかなかったりします。
治療の目標として、症状が完全に消えてなくなる、という水準を目指す、ことも悪いわけではありませんが、まずは現実的に、その症状と同居しつつ、症状に振り回されない自分でいられるようにする、というあたりを、ひとまずの治療目標にしていただくと、多少肩の力が抜けるのではないか、と思うわけです。