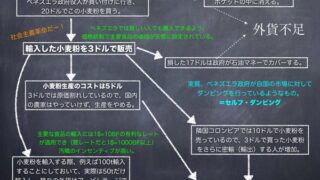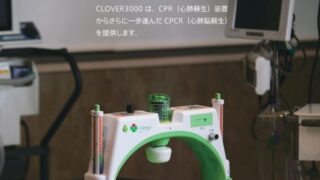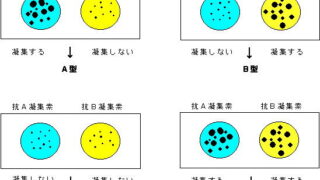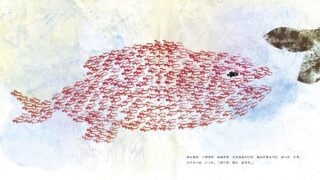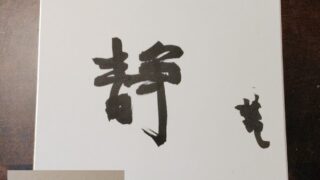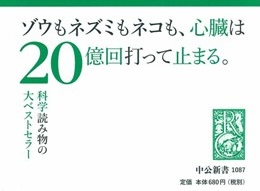漢方の流派

先日「先生の漢方の流派は日本漢方ですか?それとも中医学ですか?」というようなお尋ねをいただいたようです。
クリニックのホームページにはあまりそのあたりをハッキリ書いておりませんでしたので、見ていただいたらわかる、という話ではありませんでした。
以前も書いたと思いますが、院長のにしむら、けっこうあちこちで妙な形で勉強してきたものが、渾然一体としています。強いて言うなら、「折衷派」です…とお返事するのが正しいのだろうと思いますが、折衷派ってなんやねん!になりますよねえ…。
ええと、「せっちゅうは」と読みます。和洋折衷、なんて言葉が昔ありましたが、あれのせっちゅう、です。
せっちゅう 【折衷・折中】
(名)スル 二つ以上の考え方や事物から,それぞれのよいところをとって一つに合わせること。
「両案を―する」「和洋―の家」
わたしも漢方専門医として認定を受けていますが、日本東洋医学会という団体があります。会員数は七千人を超えているようです。
これを多いと見るか、少ないと見るか…ですが、日本産婦人科学会が一万七千人ほどだそうですから、けっこう多いのかもしれません。ちなみに、内科学会は十二万人、ということで、さすがに一桁違いました。
この七千人…だけが漢方をやっているわけではありませんが…の中に、流派がいくつかあります。
お尋ねの時にあった「日本漢方」という流れと、「中医学」という流れに分類するのが一般的なのかもしれません。
日本漢方は、江戸時代に吉益東洞(1702—1773)という人が、「『傷寒論』・『金匱要略』にかえれ」と主張したところから始まる、古い時代の処方をもっぱら用いる「古方派」というのが誕生し、それまでの流派を「後世派」と呼ぶようになりました。
純粋に「後世派」と呼ばれるほどでなく「古方」の主張も混ぜながら…という方もおられたようで、「折衷派」と呼ばれています。
また、当時流入しはじめた西洋医学(蘭方)なども併用する「和蘭折衷派」と呼ばれる方々も結構多くいらっしゃったようです。世界ではじめて、全身麻酔による乳癌の手術を行ったとされる華岡青洲は、この「和蘭折衷派」に分類されます。
とはいえ、明治時代に、西洋医学の医師のみを正しい医師とする、というルールが設定され、当時の漢方医は当代限り、となりました。
いわゆる漢方医はこの時に絶滅しかけたわけです。
それを、和田啓十郎、湯本求真といった人々が、やっぱり漢方が大事だ、と書き残し、昭和の時代に、大塚敬節、矢数道明といった人々がその系譜を受けて漢方を復興させてきた、という歴史があります(漢方薬大手の某社は、大塚敬節の指導でエキス剤に用いる生薬の種類と量を決めた、と聞いたことがあります)。
中医学は、日中の国交正常化前後に中国との文化交流をもって日本に導入された…のではないか、と思われますので、戦後のことだと考えられます。こちらは神戸中医学研究会などがその先導をされていたようです。
ひとの身体の状態と、病気がどのように起こっているのか、という病因病機論を、後世派まではずいぶんと述べていたのですが、古方派はその議論を「机上の空論」であると批判し、証に対して方剤を選べば良いのだ、という形の主張をしてきました。
現代的な言い方をすると、「かくかくしかじかの状態になっている患者にこれこれの方剤を与えれば、症状が改善する」という形の蓄積をしてきたのが古方派です。これはいみじくも現代西洋医学における「エビデンス」に近いものであるのかもしれません。
ところが、現実はそれほどクリアカットにはいきません。きっちり指定の通りの状態である患者さんはほとんど居ないわけです。それをどのように考えるのか?という調整について、古方派の先生方は、現場対応はともかくとして、理論をおっしゃいません。
後世派のままで診療をされている先生もそれほど多くないと思いますので、あとは折衷派か、あるいは中医学を併用されているか、ということになります。
実際に江戸時代には古方派の先生方も、方剤の調整をなさっておられたでしょうが、エキス剤を用いることが主流になってからは、なかなか微妙な調整が難しくなってきました。
また、明治以降の派閥として、森道伯を始祖とする「一貫堂」と呼ばれる後世派の一流派があったり、あるいは昭和から平成にかけて、江部洋一郎先生が提唱される、「経方医学」と呼ばれる一派(こちらは…『傷寒論』・『金匱要略』を中心に議論している、という点では古方派の流れと言えるのでしょうか…?だいぶ理論がきっちり組んでありますので、むしろ中医学とか、後世派の流れなのかもしれません…)があったりします。それぞれ乱立とも言える状態です。
わたしの最初の師匠は、ご自分で独自の方剤を調合していました。彼の流派を、わたしは知りません。そういえばどこで修得されたのでしょうか…?
漢方専門医を取得するためには指導医をいただくことが必要なのですが、わたしの指導医は古方派の流れをくむ、富山大学の和漢診療部のご出身で、ご自身もわりとその古方に近いところで診療を続けていらっしゃいます…。一応、指導医となっていただいたのですが、枠に填めるようなことをなさる先生ではなかったので、「きみは、そのままで良いよ」とお許しを頂戴した…ような記憶があります。
そして、大学院生時代に見学させていただいていた別の先生は、神戸中医学研究会の流れをくむ、中医学理論をバリバリに使いこなしておられた方でした。
また、フィリピンで活動をしていた助産師さんのところには、中華街で仕入れてきた「中成薬」…漢方エキスみたいなものですが、中国本土などで調合が決められていて、日本の漢方とは原材料も配合も異なるもの…がありました。もちろん、日本の漢方と同じ名前の同じ処方も、「八味丸」とか「五苓散」とかありますが、それだけではありませんでした。これらを現地でどのように使うのか?というところを考えるにあたり、中医学の考え方を取り入れる必要がありました…というか、これを現場で使いながら、あ、中医学ってこういうことなのか…と納得したようなところがあります。これまた勝手な理解ですので、本当にそれで良いのかどうか?という検討はしていません。
…ということで、とことん、野良で育ったわたしは、流派のわからない師匠と、古方の流れをくむ日本漢方の指導医と、中医学メインの先生とに、それぞれ診療を見せていただき、かつ、中医理論の方剤と取っ組み合って、それらをなんとか使いこなそうとしている、というところです。まあ、今どきの日本で、何が何でも漢方だけで治療しなければならない!と言い出すような「漢方原理主義」とでも言うスタンスの方はいらっしゃいませんし、みな西洋医学の試験を通り抜けていらした方ばかりですので、ほとんど全ての漢方医が「漢方と西洋医学の折衷」でなさっているわけです。
その上で、じゃあ、折衷している「漢方」の部分の成分はどうなってるの?って話になるんでしょうが…こちらもわたしは「折衷」という話になります。
臨床での処方構成としては、中医学寄りになりがちで、場合によっては2種類以上の方剤を併用することが多いです、といったところでしょうか。
ありがたいことに、近くで煎じ薬を処方される先生がいらっしゃるので、近隣の調剤薬局でも煎じ薬を受け付けていただいており、必要に応じて、煎じでの処方もさせていただいております。この場合の処方をどう調整するか、あたりは、やはり中医理論を援用することになりがちです。