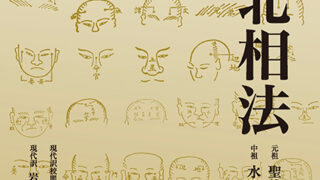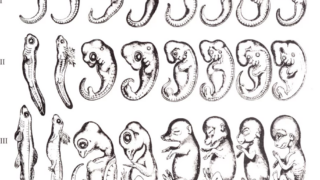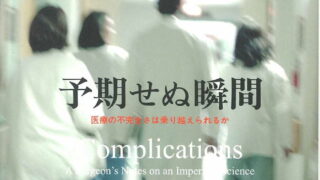漢方の診療にも人工知能が
多くの組織で、4月1日からが新年度になります。いろいろと心機一転、新しいことに取り組んで頂きたいものです。
さて。昨今は人工知能(AI)の機能もどんどん高性能になりつつあります。医師の仕事も、特に外来診療は、その多くが人工知能にとって変わられるのだそうです。
報告によると、人工知能(AI)による診療は、医師によるそれよりも、「ミスが少ない」ことと、「診療精度の変動が少ない」こと、そして、「相性があわないことがない」ことなどの利点があります。
何度同じ事を聞かれても、根気強く返答するのもだんぜん人工知能(AI)が有利ですから、そのうち全部が人工知能に置換することも遠くないのかもしれません。
漢方の診療にも人工知能によるサポートが入ることになってきた、のだそうです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000077291.html
こちらは2024年5月のプレスリリースです。
とはいえ、人工知能による診療の、いちばん難しいところは、患者さんの現在の身体状況を即座に人工知能に伝達する方法が無い、ということです。
漢方では脈をみたり、腹部に触れたりしますが、こうした触覚情報を、人工知能に伝達するためには、ヒトがセンサーの役割りをしているわけです。センサーとしてはずいぶん高級…というか、お金のかかる存在です。
とはいえ、患者さんの主観的な訴えだけで診療を行うというのも、けっこうな危険が伴いそうで、二の足を踏みます。主観的な訴えに含まれていない様々な情報が、やはりけっこう大きいわけですから、それを捨象してしまうのはいかがなものか、とも思います。
そんなことを悩んでいたのですが、このたび、脈診を代わりにやってくれるロボットが開発されました。ネーミングがひどいのですが…「脈診くん」と言います。

「脈診くん」(アプリケーションX(旧Twitter)のAIグロックによる描画)…脈ってどこで診るのかわかってます…?
そのうち、腹部の触診をやってくれる「腹診くん」も開発されるそうです。こちらは、患者さんがベッドに横たわる位置の関係などで、可動性が重要になってきます。うっかり倒れ込んで、患者さんをつぶしたり、なんてことになると大ごとですから、注意が必要でしょう。
当院も、定格化した脈診を実践するために、「脈診くん」を導入することにしました。
今後、「脈診くん」のデータを蓄積、共有することで、科学的で、再現性の高い漢方診療が実践されるようになっていくだろうと思います。
個人情報保護の時代ではありますが、匿名化した形での情報集積を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
…今日、2025年4月1日はエイプリルフールです。