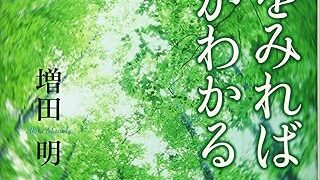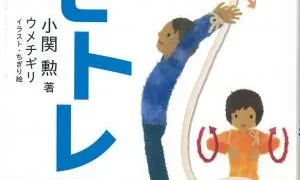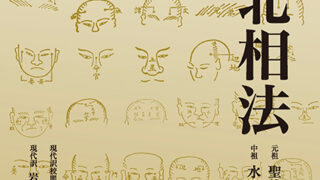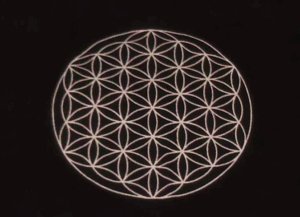漢方診療は全人的医療なのか
全人的医療がもてはやされた時に、「漢方は全人的医療だ」という主張が散見されました。
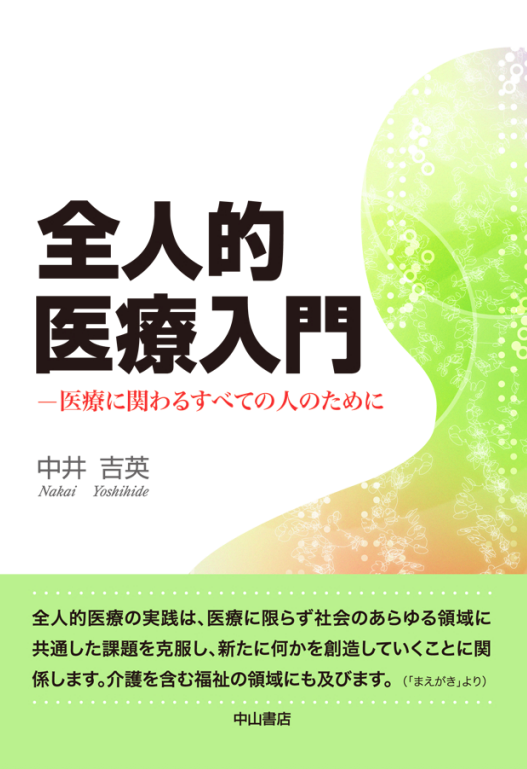
全人的医療について、考えるきっかけになったのは先日の講演会でした。そこでも、話題としては「漢方は全人的医療で…云々」という話になったのでした。
わたしみたいな折衷主義者は、いろいろな治療の良いところ取りをしたら良いのだ、としか考えていないですから、それが全人的医療だろうが、そうでなかろうが、使える範囲で使う、ということしか考えていません。どうしたって、漢方は漢方だし…と思うわけです。
とはいえ、やはり、「漢方は…」みたいな表現を見ると少し考えてしまいます。
「漢方は全人的医療なのでしょうか?」
こういう話題を出した時に、いろいろなスタイルの反応が想像できます。
たとえば、真面目に受けて、漢方診療と、全人的医療のそれぞれの共通点を探してくるスタイル。結論としては「なるほど、たしかに共通点が多いから云々」みたいな話になったりします。あるいは、「共通点はこれこれだけれど、しかし、それでは十分とは言えない」みたいな場合もあるでしょう。
もうちょっと話を拡げると「そもそも漢方診療とは」「そもそも全人的医療とは」という「そもそも主義」的な反応スタイル、というのもあります。あまり言葉を厳密に定義したりせず、ふんわりと話が進んでいる時に、いやちょっと待ってよ、と流れをぶった切る系の、どちらかというと「空気読めない」もしくは「空気読まない」系のひとが得意になってやってくる議論です。わたしもやらかしがちです。
功利主義な反応スタイルだと「だからなんやねん」というような返事をかえしてくるかもしれません。「全人的医療だったらなにか良いことがあるんですか?」あるいは「そうじゃなかったらどうだ、って言うんですか?」というような議論です。
もうちょっと混ぜっ返すと、「ところで、全人的医療であることって、そんなに良いんですか?」みたいな揶揄を含んだ逆質問のスタイルもあったりしそうです。
あるいは「主語が大きいよねえ」というようなスタイルの議論もあります。漢方診療の全てがすべて、全人的医療と言えるものではない、みたいな話になってきたりします。全人的な医療じゃない漢方診療だってあり得ます。
漢方診療は…と言い始めたときに、それはいったいどのような内容を指さしているのか?という話には、わたしは漢方オタクとして、けっこう首を突っ込みそうな気がしております。
以前も書いたように、現代の日本において、漢方を処方する医師は、間違いなく全てのひとが、西洋医学を学んで来ています。つまり、どこまでいっても、西洋医学の医師であるわけで、漢方医「のみ」で生きてきた人は誰ひとりいません。そういう「西洋医学と漢方医学の折衷派」でしかない人たちが、漢方薬を処方する診療を、まるごと「漢方診療」と呼ぶのであれば、それの内実はピンからキリまでありそうです。
漢方診療をやっていると、全人的医療を実践しやすい、かもしれない、という主張があったとして、じゃあ漢方診療をやっていない時に、全人的医療を実践しづらいのか?と訊かれると、これもまた答えに悩みます。
いやそもそも「全人的医療」という言葉の要件をきっちり定義してください、ってところもずっとあるのですけれど。
いろいろ書いてきましたが、それらの面倒くさい議論を全部放置して、じゃあ、漢方って全人的医療になるの?って話にふんわりと返事をするなら、「そもそもデカルトの心身二元論が流入してくるまで、こころとからだはひとつだった」という話になります。江戸時代の医師は、こころもからだも、一緒に診ていたのではないでしょうか。科学が入って来て、「わける」ということを頑張った結果、こころとからだへの扱いが分かれたのかもしれません。
もしくは、江戸時代のひとびとは、現代人とはべつの「こころ」があったのかもしれません。自我というものもまるで別だったのかもしれません。
漢方薬の中に、心理的な事情による不調に使えるもの、というのがあるのは事実です。
が、もともとはそれらも全部ふくめて、漢方診療の時に診る対象の「からだ」だったような気もいたします。
医学における専門の分野がどんどん詳しくなるに従って、専門家が必要になりました。だからこそ「科学」なのだろうと思います。漢方の理論は、まだ科学が十分に発達する前に成立したものを今でも使っていますから、そういう意味では、漢方の診療をするときには、こころとからだへのアプローチを同時にできる。
それを「全人的」というなら、全人的医療になるのかもしれません。