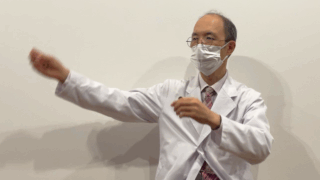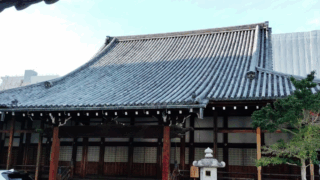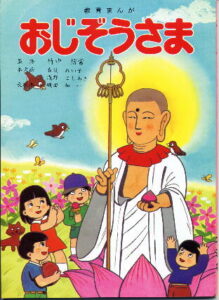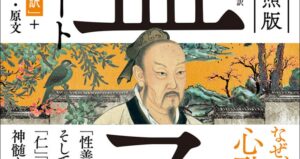理解の三段階

師匠の話を続けます…と言いながら、先日の師匠の話
…とは別の、二人目の師匠の話を、今日はします。
ボディートークの増田明氏は、理解の段階を「ふんわりと・スッキリと・しっとりと」という言い方で整理していました。
まず最初は「ふんわりと」理解するのだ、と。
これは、全体の雰囲気を把握する、というようなことです。ついつい、細かい物事が気になったり、意味をきちんと理解しようとしたりするのですが、そういう細かい部分については、ひとまず措いておいて、まずは全体的なあり方を漠然とでも良いので把握する、ということを優先させる、ということです。
そういえば、昔、絵画教室に通っていた頃に、花の絵を描く機会がありました。花びらとか萼とか、めしべ・おしべなどがけっこう複雑に入っているんですよねえ…っていう所に気が向きすぎた結果、絵の全体的なバランスはずいぶんと妙な形に崩れていったことを思い出しました。先生は「細かいものを追いかけすぎ」というようなコメントをくださっていたように思います。もうちょっと肯定的な表現でしたが…。
もちろん、細かいところも大事になってくる場合があります。「神は細部に宿る」とも言いますので、ふんわり理解だけではぜんぜん足りません。が。それでもなんでも、まずは全体の様子を、バランス良く把握することが大事なのだ、というのが、師匠の主張でした。
その次に、細かいことを整理していく、という段階が来ます。
これを「スッキリと」した理解、と呼んでいました。順序が大事なのでしょう。まずはふんわり理解。細かいところは、その次、ということです。
英語の試験では、長文読解の問題があったりするのですが、ひとつの単語の意味が気になって、躓くと先に進めない、という方が時々おられるそうです。ここも、順序が違って、まずは細かい単語の意味に引っかかる部分を、いったん括弧に入れて、全体の理解を有線する方が理解が進みやすい、ということなのだろうと思います。
全体の把握が済んだ、その次の段階で、細かい部分を詰めていくわけです。
その先「しっとりと」理解する、というのは、なかなか難しいところです。なんとも言葉で言い表しづらい。ひょっとすると、ウチの師匠、リズムが良くなるから、って後ろに足したのかもしれない…なんて邪推するくらいには、このあたりが、うまいこと表現できません。
でも、なんとなく言えることがあります。しっとりと、かどうかは別にして、スッキリと理解する、という「論理」とか「理屈」の理解を超えて、その先に、深く理解する、ということがありそうなのです。
それをなんと言うか、というあたりで、無理矢理「しっとりと」という言葉を使ったのでしょう。
指導者の育成講習では、過去の認定試験問題を、練習問題として解いてみたり、あるいはそれに対する模範解答を呈示したりしていました。
師匠はこの模範解答を、わざと、文章として成立しない形のままにしていたのが、とても印象的でした。
(それでは、スッキリした解答例が手元に残らない…というクレームとともに、苦慮しつつ、定まった文章を口述するようになった、というのも思い出深い記憶です。それぞれの言い分があるんだよなあ…と思って見ていたのでした)
ただし、ふんわり理解だと、時々、大きな落とし穴があります。
鍵となる言葉が「まるで逆の意味だった」というような話の時。全体の論調がまるごとひっくり返る、なんていうことがあります。
英語の長文の場合、重要な表現はわりと繰り返し、別の表現をつかって言い換えたりするのが一般的ですから、よほどの場合を除いて、まるっとひっくり返る、なんていうことは無いのですが、英文読解の時にわからない単語ひとつが中心にひっかかってしまった、という経験もありました。
試験の時に役に立つようにするには、やはりスッキリ理解が必要になってきますが、その前に全体をふんわりと理解することが大事、というのは、多分とても大事な智慧なのだろうと思います。
クリニックでの健康教室も、実は、わざと、細かい話をせずに、ふんわりとした話にしていたりするのでした。