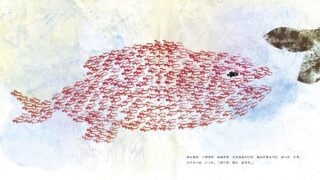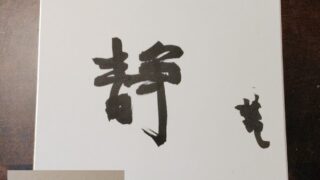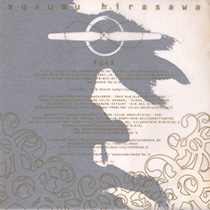理論と実践
『ご冗談でしょう、ファインマンさん』という本があります。

ノーベル物理学賞をとったリチャード・ファインマン氏が自伝的に回顧した録音がもとになった本だそうです。日本では岩波が翻訳・出版しています。
https://www.iwanami.co.jp/book/b256254.html
本当にいろいろなエピソードが並んでいる、ジェットコースターばりの展開ではあったのですが、いくつかの点がいまだにわたしの記憶に残っています。
そのいくつかは、学生時代の思い出として書いてあること。
モーメント、という概念を定義として与えられた同級生は、しかし、その定義の文章を一言一句間違いなく繰り返すだけで、それが現実世界でどのような意味を示すのか、理解できなかった
という話と、
「雲形定規の曲線になんらかの規則性があるのだろうか?」という話の時に、曲線の最下点で接線を引くと、全て水平になる、という、ファインマン氏にとっては、単に微分の結果を指摘したら、皆が実際に曲線から接線を描きだして、「本当だ!」と大騒ぎになった
という話です。
いずれも、理論をどうやって現実に応用するのか?という点について、ファインマン氏が当時の米国?の教育を批判している、という論調であったように記憶しています。
そして、似たような話は、現代の日本でも見受けられる…ような気がしています。
たとえば、
燃焼とは…有機物が酸素と化合し、熱と光のエネルギーを放出すること
こういう文章を読んだ時に、それまでにものが燃えるシーンを経験してきた人にとっては、様々な燃焼が、いずれもこの一言で説明が出来る!という部分…つまり、定義の言葉が緻密であって、かつコンパクトにまとまっていることに感激するかも知れません。
しかし、現代人はすでに管理された燃焼しか観察していないので、そもそも燃焼というものが、さまざまな様態を取る(にもかかわらず、それらを一括して言語化できる)という理解にたどり着きません。
教育を施す対象の、それまでの生活歴があまりにも変化してきていることに、現代日本の教育は、追いついていない…と言えるのかも知れません。あるいは、抽象化した概念だけを氷菓される社会において、子育てと幼児教育が、抽象的な概念に特化してきた、とも言えるのでしょうか。
いやまあ、学童の教育の話はとりあえず措いておいて。
漢方の診療をやっていると、いろいろな理論が展開されます。
わたしが中医に親和的になったのには、この、「理論と現実をきっちり地続きにする」という営為を意識的になさりつつ、教育をされている先生(金子朝彦先生)に出会ったことが、とても大きく影響しているように思います。
中医学で言う「水滞」…これはヒトの身体を構成する「気・血・水」のうちの、「水」がどこかで滞っている状態を示すわけですが…に対して、じゃあ、どのような対処を行うのか、あるいは、どうしてそれが引き起こされているのか、という部分を、日本漢方ではあまり議論しなくなっています。「水滞」…日本漢方では「水毒」と呼ぶことが多いですが…があるから、じゃあそれを治療するには「利水剤」を使いましょう、という説明がなされます。
これこれの生薬が利水作用がありますので、これらを含むホゲホゲの処方を選択しましょう…という話になるのはわかりますが、そこには、「じゃあ、患者さんは、生活の上で気をつけることってありますか?」とか「水が溜まっているなら、水分の摂取は控えた方が良いのでしょうか?」とかいう質問に答えるには、理論が必要になります。
それも、生活の水準にたどり着いて、実践に紐付けできるような、そんな理論が。
さもなければ、水滞であれば利水剤を、という対応を考えるだけになります。
これでは、薬の供給が止まった時には知識の活用ができません。
水滞だけでなく、気虚も血虚も、似たような話が山盛りあります。
これらを生活の指導にまでしっかり紐付けした理論とともに実践を行っていくことが必要だ、と、わたしは考えています。そして、そのためには、症状や口訣から一足飛びに処方を選択する、という形ではなくて、理論的に症状を分析し、それを現実に還元できるような、そういう現場での姿勢が必要だと考えています。