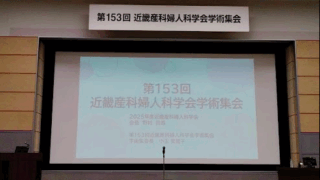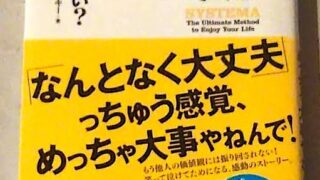胃腸が大事
「補土派」あるいは「補脾派」という系統の漢方医は「胃腸が大事」と言っています。
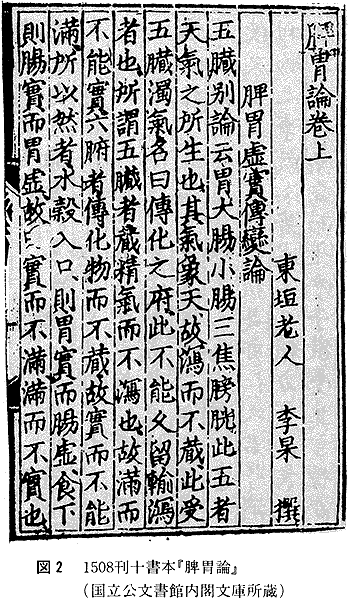
お借りしました
多細胞生物の進化を辿ってみると、生き物というのは、ざっと「円筒形」を作るようになるのですが、この時、外側の細胞が「外皮」を形成します。いわゆる「皮膚」のような場所です。そして、内側の細胞は「消化管」を作ります。

という本があります。
『ゾウの時間ネズミの時間』の
本川氏の著作です
からだの中にエサを取り込んでおいて、そこで消化吸収をする、というのが、生き物の、わりと一般的な構造なのだ、と言えるのかもしれません。(場合によっては、消化液を振りかけて、溶けた部分を吸収するような生き物もいますが…)
そういう意味では外皮と、胃腸というのが、生き物の始まりにあった部分、と言えるのかもしれません。そういう「古い」構造というのは、やはり、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。
野口整体の考え方でも、子供たちはそれぞれのタイミングで臓器を育てるのだ、という話になっていますが、いちばん最初の乳幼児期に育てるのが胃腸、ということになっています。ここが安定して育つことで、異物を取り込み、自分の一部としてゆく「同化」という作業が安定するわけです。
しっかり食べて、しっかり消化吸収できる、ということは、とても安心できることになります。逆になにか不調があるごとに食べられなくなると、いろいろと心配が増えてくることになりがちです。
日本人に比べて、欧米人は、胃腸がより頑丈です。アメリカ人はけっこう肥満のひとが多くて、手術するのに大変…という話もありますが、術後の回復力は、やはり、胃腸が頑丈なだけあって、めざましいものがあるのだそうです。
そういえば、産後の回復も結構早いとされています。あの欧米式を見習ってしまうと、アジアのわたしたちの身体では、ちょっと無理が多いのかもしれません。
漢方薬も、多くの薬が、胃腸から取り込むことになります。一部塗り薬とか、坐薬などもありますが、やはり、主だった処方は内服薬です。これらが、胃腸に入ることで、吸収されて、薬効が…という前に、腸内細菌との関わりもあるようです。
腸内細菌が、漢方薬の成分に関わることで、成分が変化し、効果を発揮するのだ、という話を伺いました。一部の処方は、なので、こうした腸内細菌がいるか、いないか、という点で効果が変化するのだそうです。
成分を有効化できる腸内細菌がいない場合はどうするのか…?というと、根気よく、少量の漢方薬を使っていると、そのうち反応しやすくなるのだとか。
これもとても興味深い話です。
昨今は腸内細菌の研究もずいぶんと進んで来ました。いちぶの疾病に腸内細菌が深く関わっている、ということが知られるようになってきていますが、同時に、漢方薬を内服されている方の腸内細菌も、良い形で変化する、という報告もあげられるようになっています。
胃腸を育てる、という話の中には、ひょっとすると、この腸内細菌叢、という視点もあったのかもしれません。
また、腸内細菌叢を考えると、脾=胃腸を「土」に分類した、ということも、大きな符合のように感じられます。
そして、この胃腸と、神経の緊張が相関しているのだ…という話があります。「腸脳相関」と呼ばれる関係性が提唱されているのだそうです。
お腹が安定すると、心理的にも安定した育ち方をしますが、心理的に安定すると、腸の状態も良い形に安定するのだそうです。
どちらから、というわけではありませんから、手をつけやすい方から。
お腹の安定と、そして、気持ちの安定を。
漢方薬もそのお手伝いができると思っています。