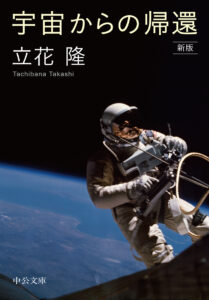覚えるために忘れる
「全力を出していたら全力が出せない!」って、そういうヘンな文章が書いてある本がありました。
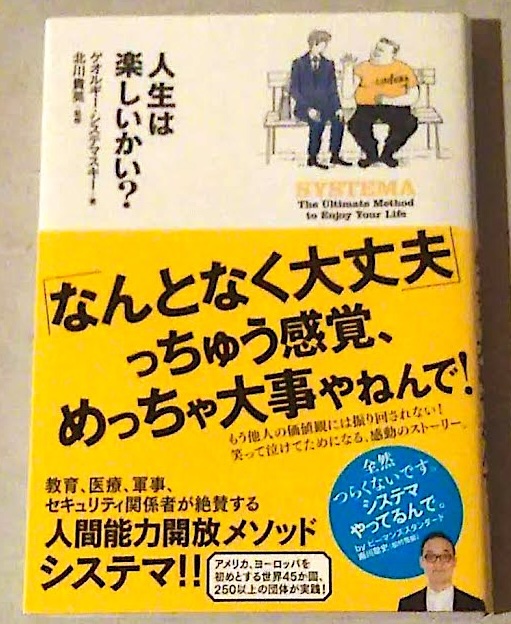
「だって、だって……全力を出してしもたら、全力を出せへんようになるやろが!」
「……?」
興奮のためか、崩壊しつつある日本語で、ゲオはさらにまくし立てた。
「だから!全力を出す、ちゅうのは全力を出すこととは違うんや!」
え。頑張るんじゃないの?って行き来があって。ここで出てきている「ゲオ」氏がシステマのマスターなんですよねえ。関西弁で喋ってますけれど。で、ちょっとニホンゴムズカシイネ、ってなって、通訳…というか、意図をもう少し上手に説明してくださる方をお呼びして、そのあたりの整理をしてもらう、という話の流れになっていました。
ポイントは「ずーっと頑張り続けていたら、『もうひと頑張り!』っていう時に出てくる余力が無いよね」という話でした。
だから、どんなに頑張っているときでも、常に3割くらいの余裕を残して、7割くらいの運行を心がけるのだ、と、そんな話でした。
この辺、「ずーっと100%で頑張っています!」っていう方もおられるのですが、この「100%」が、何の割合か、というところで、騙されているひとが結構おられるのかもしれません。
「平常に出して良い頑張り具合」の、100%、ということも結構あります。つまり、「全力の5割から7割くらい」の100%。
真に受けて、本気で「全力」の100%で頑張る方が時々いらっしゃるので…無理しないでいただきたいところです。
ええと、忘れることと、思い出す訓練が、というのは、野口整体の野口晴哉氏が書き残しておられます。
人間は、人間の習性としても記憶しようと努力するのです。
しかし潜在意識は、一度あったこと、触れたこと、見たことは全部忘れないのです。新しいことはみんな頭の中に記録されているのです。
殊更にこれだけを見ようと偏って見ると、それだけしか見えないことがありますが、偏りさえしなければ、みんな平均して記録されているのです。
だから想い出す訓練をすれば、すぐそれを取り出すことが出来るのです。ところが、勉強だけに集注していると、そのことが濃く入っているので、思い出そうとしても、そのことだけしか想い出せない…(中略)…山が当った時は吃驚するほどの成績をあげますが、外れたらそれこそ最後です。
それは、それだけに集注して、他を想い出さないからです。そういう勉強法ではなく、平らに勉強して、ときどき想い出すという訓練をすることが、一番大切です。
例えば、英語の単語を夜、寝る前に二十なり三十なり覚えようとする。そして覚えたと思ったらそのまま寝てしまい、朝になって床の中で想い出す。
それを全部想い出すまで毎日続けると、大抵一週間ぐらいで想い出します。…(後略)『思春期』野口晴哉著、全生社
いったん頭に入れておいて、あとはすっかりスッキリ忘れてしまう、ということをやると、頭の負担も軽くなるし、くたびれなくなる…というようなことも書いておられました。
この「すっかり忘れる」というのが肝腎で、これをしないで頭の中にとどめておくと、だんだん、頭が大変になってきます。
普通…ってどのあたりを普通と呼ぶのか、は今ひとつ悩ましいところですが…は、そんなに何もかも頭に詰め込むことは難しい、はずなのです。が、時々、それを実践してしまわれる方がいらっしゃいます。
博覧強記のまま、全て覚えたままで勉強をされている方、本当にどうやってそれだけいっぱいの物事を頭に詰め込んだままで生活ができるのか、というあたりは不思議なのですが…。
どのくらい、詰め込んだままの状態を続けられるのか、は、その方の頭の容量と、それから、詰め込む情報の圧縮具合によっても違うのだろうと思います。
たとえば、講義をされている先生の手の動きとか、服の模様とかを含むような些細なことまで覚えておられると、よほどの容量が無いと、そんなに博覧強記を続けることはできません。そうした枝葉末節的な部分を捨象するのであれば、もう少し容量が少なくても、結構な内容を抱えることができる、ということだってあるでしょう。
とはいえ、人生を生きていると、どこかで「持ち続ける」という方法は破綻します。破綻の前後に、頭痛を伴うことが多いようです。
頭痛とともに、頭の整理が済み、「頭がスッキリする」とおっしゃる方もありましたが、さすがにそれまでの頭痛がとても大変ですので、あまりお薦めできる方法ではありません。
これを回避するためには、やはり、「いったん忘れる」ということが重要なのですが、今まで忘れる、という形で頭の整理をされたことがない方の場合、どうして良いのやら、ということになるようです。
当院、そういう十代の方が時々お越しになります。
上手に忘れて頂けるようになると、頭がスッキリ空っぽになりますので、頭の性能を万全に発揮できるようになってきます。場合によっては、ここに漢方薬を併用することもありますが、一度やり方を覚えて貰って、それで済む場合もあるようです。
もちろん、全ての方の頭痛がそれだ、とは申しません。
たまには、そのような頭痛もあるのだとご理解ください。