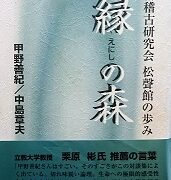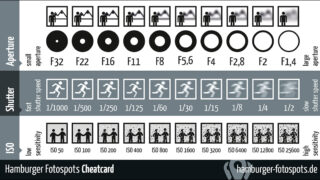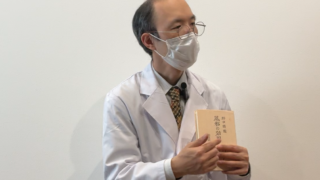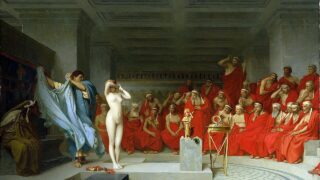過ぎたるは及ばざるがごとし

昔、「叩いて強くなるのは餅と鉄だけだ」とおっしゃった方があったそうで、そんな話を講習会の時に聞かせて頂きました。
餅はコシが出るんでしょうが、ひとは、体罰で叩いて指導したから強くなる、とはならない。体罰では成果に繋がらない、みたいな話だったように記憶しています。
体罰の効果や是非の話ではないのですが、一般的になんとなく、正しそうに思われていても、よくよく考えたら「あれ?おかしいぞ?」と言いたくなることもしばしばあります。
そのひとつ。
「こういうコトをすると、身体に良い」とされること、って、けっこういろいろあります。先日の学会に参加したら、そんなサプリメントの案内が山盛りありました。
いわく、腸内細菌を…。
いわく、発酵食品を…。
いわく、血流の改善を…。
などなど。
これ、どれもおっしゃるように効果的であるとして、じゃあ、これ全部を毎月摂取し続けたら、いったいどれだけお金かかるの?って思います。
そんな話を考えていた時に、良いたとえ話を提供してくださった方がありました。
食パンをトーストすると美味しくなります。
じゃあ、倍の時間トーストしたら、倍美味しくなるのか?っていうと、そうではありません。
むしろ、焦げてしまって、食べられなくなります。
物事には「適量」っていうのがあるのだろうと思います。
適量がある、っていうことわざが、冒頭タイトルの「すぎたるは及ばざるがごとし」です。
野口整体の野口晴哉氏は、治療には「機」「度」「間」が肝腎なのだ、という文章を残されています。
「機」:良いタイミングに、
「度」:ちょうど良い量の働きかけを行い、
「間」:その反応を待つ時間をとる
…ということですが、じゃあ、どうやって、その「良い具合」を見つけるのか?というと、これは、言葉で説明できるものでもないようです。
いちばん大事なことが、文字にならない、というのは本当に頼りないことこの上ないのですが、まずは、「これが良いって言われたから…」という「あたま」での判断をいちど止めて、今、ご自分の「からだ」が何をどう感じているのか?をしっかり拾いあげることに意識を向けて頂くと、少し分かりやすくなるかもしれません。
良いものだと言われている、そのことも、それぞれ「適量」があったり、あるいは、互いに邪魔しあったり、組み合わさることで悪いものになったり。そんなことだってあり得ますので…