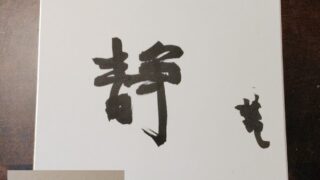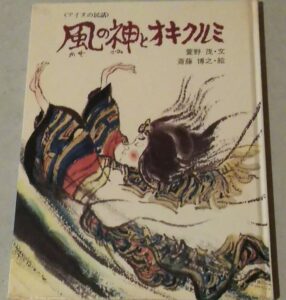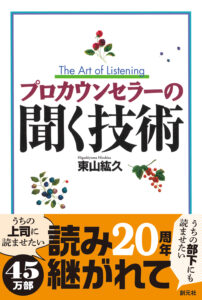難しい病気

世の中にはいろいろな難しい病気がある、とされています。
昔、軍医だった先生が「死なない病気はみな治る!」と豪語されたという話を聞いたことがありますが、なかなかそういうわけにもいかないのが最近の様子です。
「死ぬ病気」と「治る病気」以外に「死なないけれど、治らない病気」というのもありそうです。
難病が増えてきた理由は、食事や添加物が…とおっしゃる方もあれば、環境の破壊が…とおっしゃる方もあります。平成の初め頃でしょうか…?話題になった「脱パンツ健康法」というのがありましたが、その源流にある『健康であるために ゴム紐症候群について』の著者である見元先生は、衣料におけるゴム紐の使用がややこしい病気を増やす原因になっているのだ、と書いておられます。
どこまで本当なんだろうか?とは思いますが、「原因」の話をするならば、そういう様々な物事の複合した結果、と言えるのかも知れません。
症状というのは、氷山の一角のようなものですから、それを支えるいろいろな不調があるわけです。
体調が悪い、とか、よく眠れなかった、あるいはストレスが大きかった、疲れていた、食生活が乱れていた、頭を使い過ぎた、心配事が多い、などの状況が重なって、そこに加えて外的要因で気温の変動だったり、暑かった、寒かった、あるいは花粉が飛んでいる、ダニが、ハウスダストが、あるいは食事にアレルゲンが、などの要素がかかわります。
大きな原因を取り除くことができるなら、それで症状は解消しますが、取り除けるような大きな原因が無い時には、体調を整えていくとか、しっかり眠れるようにする、とか、そういう、日常のことをひとつずつやっていく必要があるのかもしれません。
漢方医学的な話をすると、西洋医学的に難しい病気が、漢方の見方をすることで、それほど難しくない病気として対処できる場合があったりします。もちろん、漢方的に見ても、それでも難しい病気のままであることもありますので、必ず、とは言えませんが…。
漢方の勉強会に行った時に、講師をされていた、故、江部洋一郎先生は講義の中で「漢方理論では五臓と気血水しか無いわけだから、あらゆる疾患はこの5×3の中のどこかに入るのだ」とおっしゃっていました。また極端に乱暴な一般化じゃないのかなあ?とは思いましたが、もともとの理論自体がそういう思弁的な話ですから、まあ、どこかに収まる…ようにするのだと思います。
漢方ではそんなに難しくない、なのか、やっぱり漢方でも難しい、なのか、どちらの状態でおられるか、は直接お目にかからないと分からないところもありますが、多少なり、明るい方向性の話題にはできるように思いますので、よろしければ一度ご相談くださいませ。