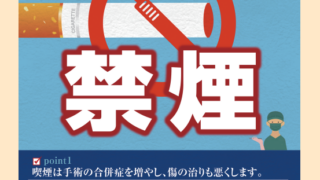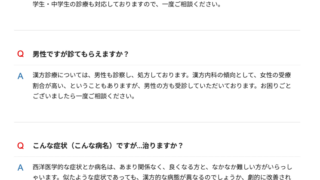顧客が本当に必要だったもの

SNSのミームになった画像のひとつに「顧客が本当に必要だったもの」というのがあります。
ピクシブ百科事典に細かい解説とともに記事がありました。
1枚の絵の中に、枠があって、10個の絵が描かれています。
「顧客が説明した要件」
「プロジェクトリーダの理解」
「アナリストのデザイン」
「プログラマのコード」
「営業の表現、約束」
「プロジェクトの書類」
「実装された運用」
「顧客への請求金額」
「得られたサポート」そして
「顧客が本当に必要だったもの」
それぞれに、面白い絵が描かれていますので、いちどご覧になっていただくのは良いのかも知れません。
これは寓話ですので、実際にその形を目にできるようなものではない、プログラムとかシステムの話を揶揄したものであったようです。
つまり、要件の定義がきっちり詰められていないと、その先でいろいろと困るよねえ…というような話だったのでしょう。
こういう絵を見て「だから素人さんが口出しするのは難しいのだ」とか、そういう批判は、わりと簡単に出てくる…のかもしれません。
顧客の希望をきっちりと聞き取るのがプロジェクトリーダの仕事じゃなかったの?という言い方もある、かもしれません。
要件定義をきっちり詰めるところを、顧客側が行うか、それとも、システムを組む側が請け負うか、というあたりは、最初に決めておくべきことでしょうけれど。
ところで、「病者の祈り」と呼ばれるテキストがあります。
苦難にある者たちの告白
私は神に求めた、成功をつかむために強さを。
私は弱くされた、謙虚に従うことを学ぶために。私は求めた、偉大なことができるように健康を。
私は病気を与えられた、よりよきことをするために。私は求めた、幸福になるために富を。
私は貧困を与えられた、知恵を得るために。私は求めた、世の賞賛を得るために力を。
私は無力を与えられた、神が必要であることを知るために。私は求めた、人生を楽しむために全てのものを。
私は命を与えられた、全てのものに楽しむために。求めたものはひとつも得られなかったが、願いはすべてかなえられた。
神に背く私であるのに、言い表せない祈りが答えられた。私はだれよりも最も豊かに祝福されている。
日本語訳はもう少し文学的なものもあるのですが、こちらの方が現地の写真を撮っておいでのようでしたので、このまま引用させていただきます。
ちょっと調べると、どうやら、南北戦争当時のどなたかの文章である…?などという記述もあるようです。
ひとの心は、場合によって、自分にも嘘をつく、ということがあります。
本当に必要だったもの、というのは、きっと、自分自身の中でもわからないことが多いのでしょう。
求めているものと、必要なものがズレている(…ということを、自分自身が気づいていない時に、いったい誰がそれを知るのか?というところも結構難しい話ではありますが…)時に、それをどう自分のなかで(あるいは周囲との関係のなかで)折り合いをつけるのか、っていうのはとても難しい話になってしまいそうです。
言葉というものは、いつまでも、どこまでも「言い足りない」か「言い過ぎる」か、のどちらかだ、とおっしゃった方もありました。
ことば、というものを、を万能だと思っていては、勘違いしてしまうのでしょう。
とはいえ、わたしたちは、言葉に頼って生きているわけですから、何らかの形で思いを言葉に載せてゆくしか方法がありません。
このあたりが、いつも、難しいところだなあ、と思います。