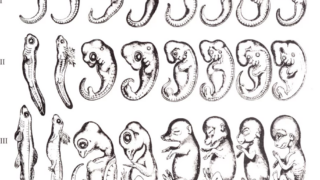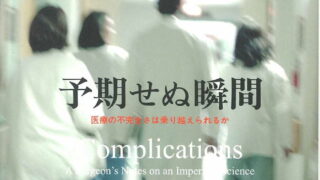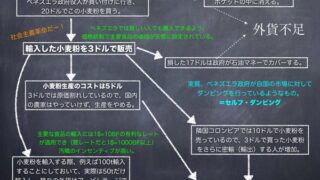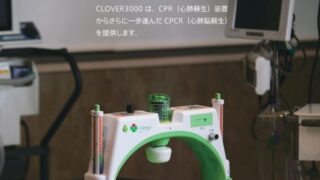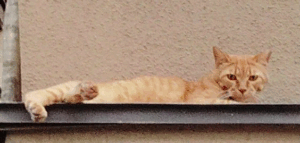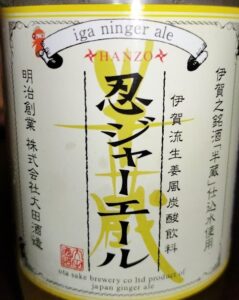馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を飲ませることはできない
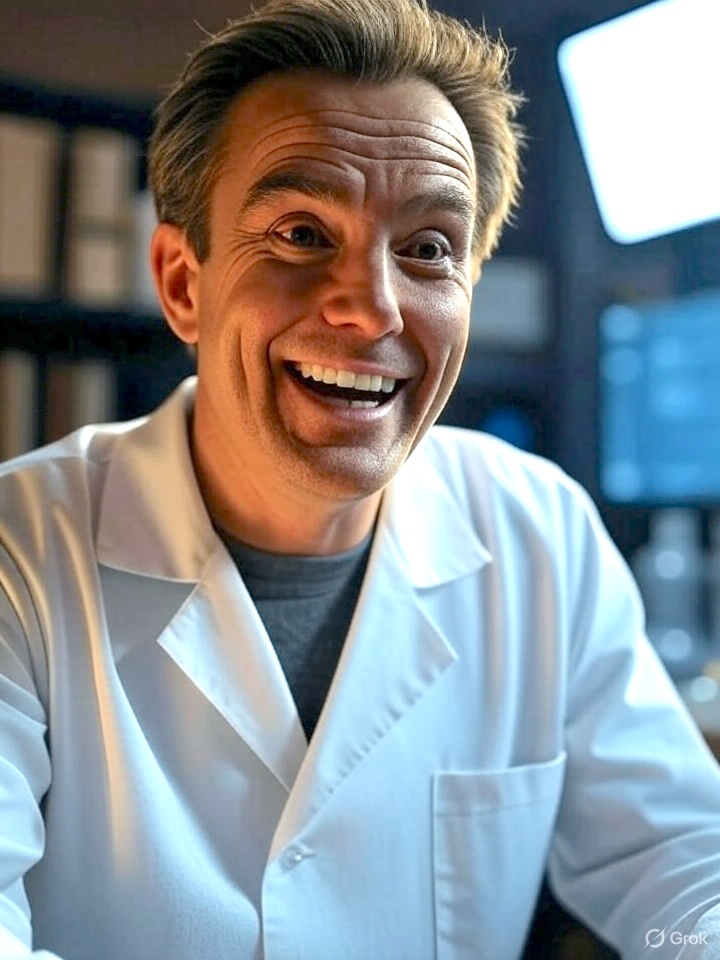
マッドサイエンティスト風
医療関係者
「強制的に水分を摂取させる方法ですか?ええと、医療行為の中にはいくつかあります。ひとつは、胃管などの管を消化管の中まで送り込んで、その中に半消化物とか、あるいは、水分を送り込む方法ですね。長期化する場合には、皮膚から胃に向けて穴をあけて、胃瘻という形にすることもあります。この胃瘻の良い点は、水分や食物がのどを通過しないので、誤嚥が極めて少なくなる、というところにもあります…。」
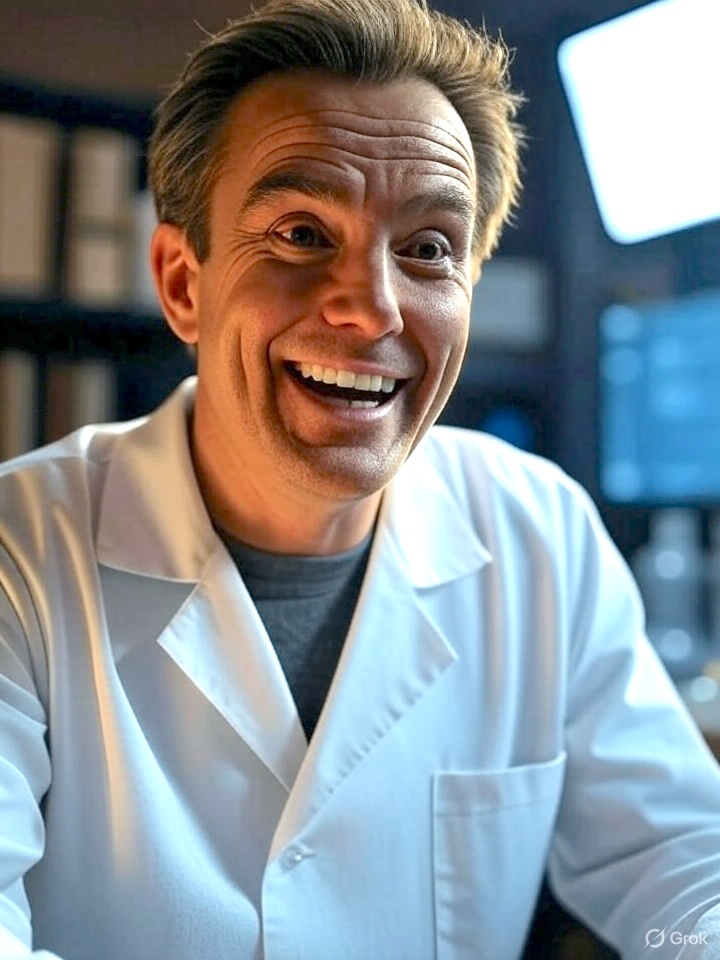
マッドサイエンティスト風
医療関係者
「もうひとつは、点滴ですね。血管の中に針を留置して、そこに電解質などを調整した水分を滴下してゆきます。こちらの問題点は、あまり濃度が濃いと浸透圧の関係で血管痛が発生したり、あるいは血管からの漏れが発生したりすることと、長期間留置する場合に感染のリスクがある、ということでしょうかねえ…。」
…って、そういう話ではなくてですねえ。
モチベーションの話を昨日、少ししたところでした。
先日、モチベーション…つまり動機付けについて、ちょっとした講義を聴いてきたのでした。
モチベーションには大きく分けて2つあるのだ、というのです。
ひとつは「内発的」。そしてもうひとつは「外発的」。
内発的な動機付けというのは、つまり、馬が水を求める、というようなものです。のどが渇いた、というのは、身体的な欲求ではありますが、それに近い形で心からの欲求があったときに、それを内発的と呼びます。

外発的な動機付け、というのは、どういったら良いのでしょうか。馬などであれば、鞭を打たれるとか、あるいは鼻を引っ張られる、とかでしょうか。馬(あるいは牛)を飼っている人間の思ったとおり(に近いように)動かねば、苦痛が続きます。
ヒトの場合であれば、評価される、賞賛される、あるいは、逆に叱責を受ける、というようなことが「外発的動機付け」になりそうです。
あれ?どこかでそんな話をしたことがありますねえ…?
行動分析という話をちらっとしたことがありますが、この「報酬」というのが、まさに「外発的動機付け」の枠組みにぴったり来そうです。
ところで、行動分析の中では、「思考」それ自体も行動であると考えています。そして、この「思考」に対しても、報酬の考え方が成立します。
ということは、「内発的な動機付け」と呼ばれているものの一部には、こうした「外発的動機付け」によって誘導された思考が紛れ込んでいても不思議ではありません。
実際に、最近の研究では、外発的・内発的、という形でくっきりと弁別できるものではなさそうだ、という話に進んでいるようでした。一安心したところです。
ひとが、自分の中で「変わろう」と思っている時であれば、ほとんど何をしなくても、そのひとは変化していきます。些細な後押しで十分です。
逆に「変わろう」と思っている時でなければ、どれだけ周りが力んでみても、頑張って見ても、そのひとは変化しない、ということになります。
このあたり、いろいろと難しい。
わたしたち医者は、医療の技術というものを持つようになりました。これらの技術は、他人を無理矢理に変化させることを含んでいます。冒頭の「強制的に水分を身体に届ける」というのも、1つの技術です。
こうした技術によって、元気になっていく方もあります。が、どこまで行っても、最終的に生きる主体はその人にあります。その人の主体性を奪ったままで、医療者が生かし続ける、ということもおかしな話にしかなりません。
医療の話に限らず、ひとを救済する、という話は、どれもこれも、ひとのあり方を変容させてしまうわけですから、勝手に救済する、というのは、本当に「小さな親切、大きな迷惑」になりかねません。
治療家は多少なり、おせっかいでなければなりませんが、かといって、踏み込みすぎてもなりません。この辺の線引きがいつも難しいところです。