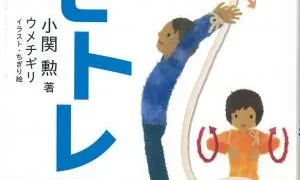鬼に金棒・豚に真珠

わたしの思い出話ですが、大学生の夏休みに、イギリスにホームステイし、語学研修とボランティア体験、という形のプログラムに参加したことがあります。
当時、ちょうど円高のいちばん進んでいた時期だったでしょうか。バブルは遠ざかりましたが、海外旅行に行く学生も社会人もそれなりにまだ多かったように記憶しています。
ホームステイ先のホストファミリーには、ずいぶん良くして頂いて、海に連れて行ってもらったりしたのを覚えています。
ある時のホストファミリーとの食事が、フライドポテトでした。ホストマザーと、そこの娘さんとが、一生懸命ポテトを揚げておられたのですが、カリッと、色が変わったポテトを、油から引き上げるのを、ずいぶんと苦戦しておられました。
網ですくっていたのか、お玉みたいなものを使っておられたのか。ともかく、本当に不自由そうだなあ、と見ていたわたしは、「そうだ。日本に帰ったら、菜箸を買って、ホストファミリーにプレゼントとして送ろう」って思いついたのです。
良い考えでしょ。
…って考えた直後に、自分の考えを否定しました。ダメダメ。
箸って、ただの棒きれじゃないですか。あれは、道具だけでは完結していなくて、それを使うひとの技術が重要なポイントになるわけです。今なら、トングみたいなのがありますが、そうじゃない、竹の菜箸では、とても、使えたものではありません。
余所のひとが、その場所で長いこと続けておられる習慣、っていうのは、それなりの理由があるわけです。工場のマニュアルは、血で書かれている、という話もしばしば目にします。つまり、「そんなまどろっこしいことやってられるか!」って横着をしたところで、死亡事故が発生したりした歴史があるからこそ、それをマニュアルとして残すようになっているわけです。
そうした経緯や、歴史を把握せずに、今の目の前だけ見て変更を!と叫んだところで、それは実現しないか、あるいは実現したところで大きな事故を引き起こすか、ということになりかねません。
そういう、文脈とか、運用方法のシステムとかが、重要なものはたくさんあります。
これもずいぶんと前の話になりましたが、商社づとめの知人に、日本から輸出できるもの、って何か?みたいな話を聞いたことがあります。2000年ころの話だったでしょうか。彼いわく「コンビニ」だと。
その後フィリピンに訪問するようになってから、セブンイレブンがどんどん店舗を増やしているのを見ました。
なるほど。これのことだったか…と思いながら見ていますが、フィリピンのコンビニエンスストアは(コンビニエンスストアに限ったことではありませんが)入口のところに、銃を持った警備員が立っています。
物流の安定性や、治安の問題など、コンビニエンスストア、という業態を輸出するにあたって、現地に適合させるために、どれだけの苦労があったのだろうか…と、関係諸氏の奮闘には頭が下がる思いです。
医療の現場でも、以前「湿潤療法に思うこと」と題してブログに書きました。
フィリピンの状況では、閉鎖湿潤療法を行うよりも、開放して、乾燥させるほうが、ずいぶんと治療が進む環境だったのだろうと思います。
そういえば、日本の炊飯は「赤子泣いても蓋とるな」ですが、フィリピンのお米を炊くときは、水加減が最初から適当で、時々蓋をあけて、炊け具合を確認しながら、水を足したり、あるいは蓋をあけて、蒸発量を増やしたりすることを当たり前にされているのだそうです。
日本のやり方を…としばらく工夫されたそうですが、なにぶん、そもそものお米の状況が場合によって異なるらしく、炊飯器を使うのも、蓋をしたままで炊くのも、とても難しいそうで、結局現地の人たちのやり方が最も合理的であることがわかった、と、冨田さんには聞きました。
郷に入れば郷に従えとは言いますが、個別の事情には歴史があります。そういうことを配慮してゆきたいものです。
ちなみに。
ドラマなんかでは超絶技巧の外科医が手術を上手にこなして、「あとはよろしく」という話がしばしば見られますが、病院によっても術後管理の方針が違う場合があります。手術の時の詳細と、術後管理の方針とがずれると、周術期合併症を引き起こすこともあります。単純に手術「だけ」では成立していないのだなあ…と、しみじみ思ったことがありました。