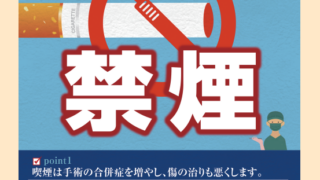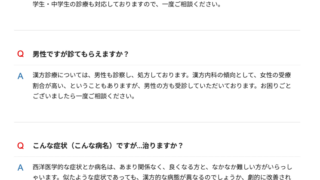3D禁止令
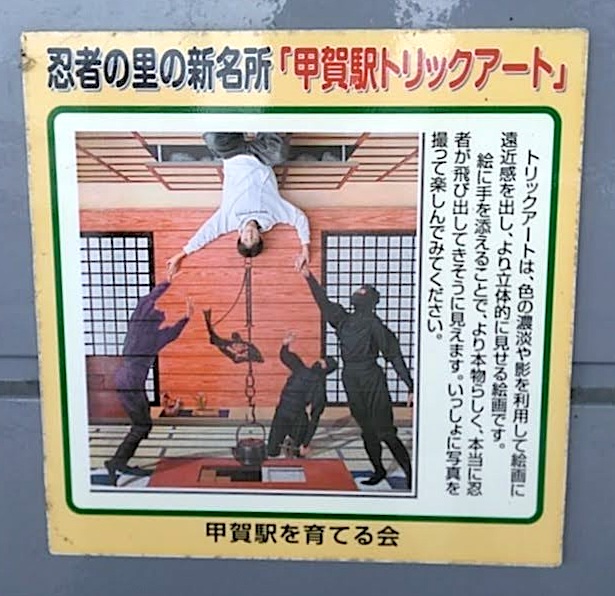
わたしは高校生の頃、吹奏楽部に所属していたのですが、「3D」っていう教則本があって、基礎練習として、合奏のはじめに、この楽譜を揃って演奏したりしていたのでした。
今でもあるのかしら?と思ったら、販売してますねえ…。『3D バンド・ブック よりよいバンドのための3つのアプローチ』というタイトルらしいです。
https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01096692
この3Dバンド・ブックは、楽曲練習に入る前の予備的な練習として、もっとも効果的な3つの次元(Dimension)によるアプローチの方法を示したものです。全体は次の3つの部分から構成されています。
なるほど。3Dって3つの次元ってことだったんですね。いわゆる立体を3Dって呼ぶのと、基本的には一緒でした。縦横高さの三方向を指す3Dと、音楽における「3つの次元」ってのは別の話ですけれど。
そんな話をボンヤリと思い出したのは、別の方から「学生時代に…」って話を伺ったから、かもしれません。学年主任だったか、校長先生だったか、わりと教育に熱心な方がおられたのだそうですが、その方が「3D禁止令」というのをお出しになったのだそうです。
楽曲演奏の前のレッスンの話でもなければ、奥行きが追加された任天堂のゲーム機のことでもありませんでした。
「でも」「だって」「どうせ」
どれもローマ字で書くとDで始まります。この3つのDで始まる言葉を使うのを禁ずる、ということだったようです。
こういう言い方をするのも、いろいろと問題があるのですが、その学校は、当時、あまり学業の成績がふるわない方が集まってくるところだったのだそうです。そういう、学業が得意じゃない、という認識が学生さんの方にもあり、また先生もどこかで諦めが出てくる…と、何か新しいことに取り組もう、と思った時にも、3Dが出てきて、すぐに自分たちで自分たちの勇気をくじくことになります。
もちろん、いろいろとやってみたけれど、どうしても届かなかった、ということだってありますが、悔しい思い、残念な思いを重ねると、最初から諦めムード…というような傾向が出てきたりします。
その「端から諦めている」ムードでシラケると、頑張らなくなります。
3D禁止!とおっしゃった先生は、歯がゆい思いをされていたのでしょう。きっちり頑張って、本気で挑んでもいないのに…ということが繰り返されたのかもしれません。
世の中では「できない理由を探す」という言い方をされることもあります。
どのような事でも「できる」と言い立てることが本当に建設的かどうかはまあ、おいておくとして、少しずつ、自分の軸を建ててゆくこととか、自分の力を取り戻していくことを、「でも」「だって」「どうせ」で諦めて、自分自身をないがしろにし続けるのは、ある種、自分自身に対する暴力…あるいは自傷行為です。
頑張り続けることも大変な場合があります。休むことだって大事なしごとです。しっかり休んで、体力を回復させたら「でも」「だって」「どうせ」を振り捨てて、挑む、ということも、人生の中では大切なのだということを、覚悟していただきたいなあと思います。