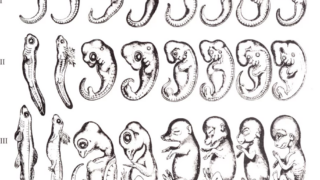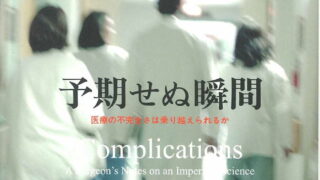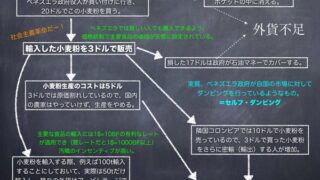少なく学べば偏見になる。多く学べば智慧になる。
先日、わたしの母の考えと、わたし自身の考えが違うのだ、ということに気づいた時の話をちょっと書きました。
無謬だったころの母は、それでもわたしにとって、かなりきつい矛盾を作っていた、ということがありました。
わたしは三人兄弟の真ん中なのですが、兄と、弟がいます。
まだ若い頃、結構年の近い兄弟と、しばしば喧嘩をしたのでした。
母は、それぞれ平等に叱り、教え諭した…らしいです。
兄には「お前は兄なのだから、我慢しなさい」と。
弟には「お前は弟なのだから、兄を立てなさい」と。
それぞれ「平等」に。
他の兄弟の見えないところでやっていました。
きっと、兄はそれで「我慢しなさい」というメッセージを一貫して受け取っていたのだろう、と想像しています。
弟は弟で「兄を立てなさい」というメッセージを一貫して受け取っていたのではないでしょうか。
わたしは、兄と喧嘩すると「弟だから」と言われ、弟と喧嘩すると「兄なのだから」と言われたのでした。
この一貫していなさに、だいぶ振り回された記憶がありますし、この話をそれなりに「客観視」して人様に話すことができるようになった時には、ずいぶんと涙が出たものでした。
そんな話を受け止めてくださったのが、東山紘久先生でした。
東山先生のことは、以前、ほぼお名前だけですが、触れたことがありました。本当にたくさんの先生方に恵まれたなあ、と改めて思います。
東山紘久先生、世間的には『プロカウンセラーの聞く技術』というロングセラーの本の著者として知られているかもしれません。
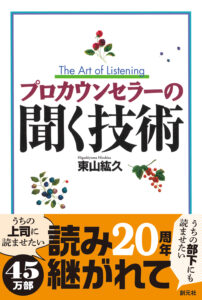
東山先生の講義にもぐり込んでは、いろいろとお話を伺いました。
先生のおっしゃるには「世の中には正しいことがたくさんあるのです」という言い方をされていたのが、衝撃的でした。
それまでは、母が「どこから上っても富士山は富士山。真理はひとつ」という形で言い切っていました。なんだかそういうものだ、と思っていたので、正しいことはひとつ、だと思い込んでいたわけです。
なるほど、そういう言い方があるのか…。と目から鱗が落ちる思いをしました。
「少なく学べば偏見になる。多く学べば智慧になる」というのも、先生から教わった言葉です。
先生が、小学校の教育実習に入ったところで、授業の時間割を児童たちの希望で組んで、毎日体育ばっかりしていた…ら、次の週くらいになると、子どもたちから「やっぱり(好きな)体育ばかりじゃなくて座学も入れないと」という言葉が出てきた…(親に指摘されたので反省したらしい…)というエピソードも衝撃的でした。
養護学校の校長をされていたときに、卒業式の計画を生徒にまるごと任せた、という時の話もなかなか興味深い話がありました。意気揚々とプレゼンする生徒に「これ、雨が降ったら、どうするんや?」って尋ねたら、「雨は…降りません!」って返事があったのだそうです(とはいえ、次の計画にはちゃんと雨の場合の対策も盛り込んであったのだということでした)。
来談者中心療法をとことん実践されていたのかもしれませんが、『遊戯療法の世界』という本の中でも、教え子さんたちが、子どもたちの遊びにとことんお付き合いすることで、大きな変容を経験する、というエピソードがちりばめてありました。
これもまた、相手を尊重する姿勢から出てくる実践であったのかもしれない、と今振り返って思います。